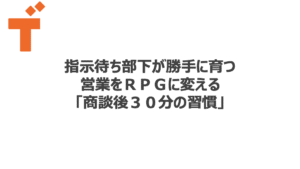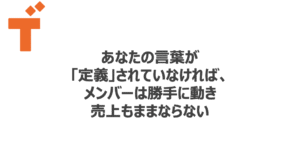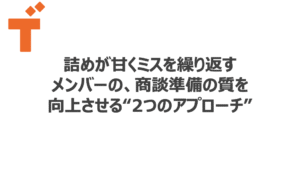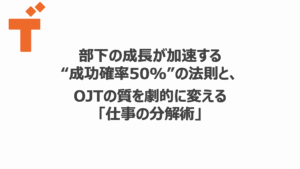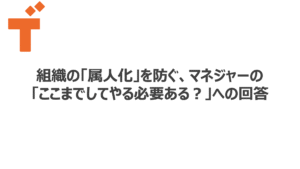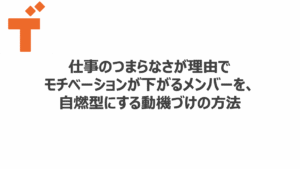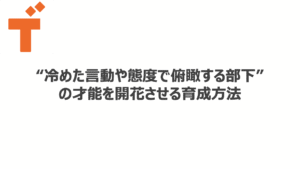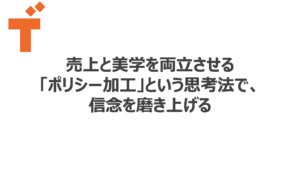「激務は経験した方がいい」は本当か? 営業のプロが語る“修羅場”経験の光と闇
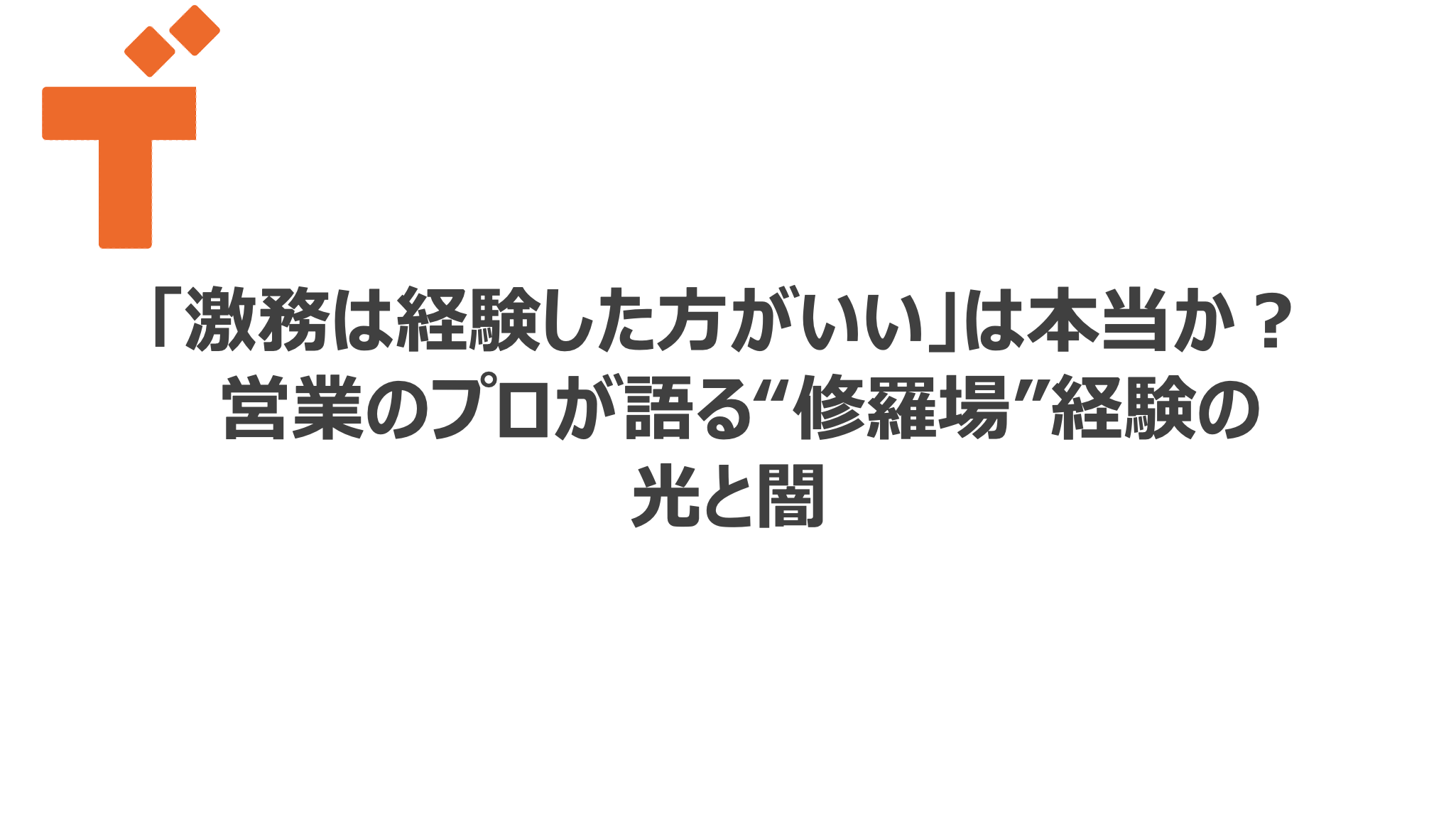
「いやー、うちの会社、マジで激務でさ…」
この言葉を聞いて、あなたの頭にはどんなイメージが浮かびますか? 「休日返上」「終電帰り」「鳴りやまない電話」「厳しいノルマ」…もしかしたら、「ブラック企業」「やりがい搾取」といった、ネガティブな言葉が真っ先に思い浮かぶかもしれませんね。
特に、働き方改革が叫ばれ、「ワークライフバランス」が重視される今の時代、「激務なんて、もはや時代遅れだ」「そんな経験、しないに越したことはない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、一方で、今の40代、50代、あるいはそれ以上の世代の経営者やベテラン営業マンの中には、「若い頃の激務経験があったから、今の自分がある」「一度は修羅場を経験しておかないと、本当の意味で仕事はできるようにならない」と、激務を肯定的に語る人も少なくありません。
一体、どちらが正しいのでしょうか? 激務は、本当に経験すべきなのでしょうか? それとも、百害あって一利なしなのでしょうか?
このコラムでは、私自身が営業職として十数年間、その中でも特に「ブラック」と呼ばれてもおかしくないベンチャー企業2社で、文字通り「馬車馬のように」働いた経験を踏まえながら、「激務」という経験が、私たちのキャリア、特に営業や経営の世界で生きる上で、一体どんな意味を持つのか、その「光」と「闇」について、徹底的に掘り下げてみたいと思います。
この記事を読み終える頃には、「激務」に対するあなたの見方が、少し変わるかもしれません。そして、自分自身の働き方や、部下・後輩への関わり方について、新たな視点を得られるはずです。
貴社の営業力を飛躍させる「実践型」コンサルタント
ベンチャー・大企業合わせて約20年以上営業現場経験を武器に、貴社に再現性のある「売れる仕組み」を構築します。
現在も営業職として現場の泥臭さを経験しているからこその営業視点を強みとして、座学研修のほか、今日からすぐに使える実践的なノウハウで、特に商談・プレゼン力の向上に貢献します。
「売上を伸ばしたいが、何から手をつければ…」とお悩みの経営者・営業部長様へ、実践型コンサルティングで、貴社の営業チームを強化し、確かな成果へと導きます。

「最近の若い者は…」は本当? 変化する「激務」のカタチ
まず、大前提として押さえておきたいのは、「激務」という言葉の意味合いが、時代とともに変化してきている、ということです。
2010年代後半からの働き方改革の流れもあり、かつてのような「24時間戦えますか?」的な、モーレツ社員を是とする風潮は、明らかに薄れてきています。
コンプライアンス意識の高まりから、組織の先輩や上司、経営者も、うかつに「無理な働かせ方」を指示できなくなりました。これは、社会全体としては、非常に健全な変化だと思います。
しかし、その一方で、新しいタイプの「激務」が登場してきているように感じます。それが、私が勝手に「セルフ激務」と呼んでいるものです。
「セルフ激務」とは、会社から強制されるわけではないけれど、自分自身で、家に帰った後も深夜まで仕事をしたり、休日も自主的に勉強会に参加したり、スキルアップのために副業に励んだり…と、自らを厳しい状況に追い込んでいく働き方です。
これは、将来への投資や自己成長への意欲の表れであり、非常に尊いことだと思います。
一方で、私のような1970年代後半〜80年代の世代が、若い頃に経験した激務は、これとは全く性質が異なります。それは、「やらされ激務」とでも言うべきものです。
自分の意志とは関係なく、膨大な業務量が降りかかり、達成不可能な目標を課せられ、結果が出なければ人格否定に近いような厳しい叱責(しっせき)を受ける…。まさに、「死ぬほど働かされる」という表現がぴったりくるような環境でした。
この「セルフ激務」と「やらされ激務」は、似て非なるものです。 本当の意味での「激務」とは、後者の「やらされ激務」のように、自分の意志ではコントロールできない、圧倒的な外部からの圧力(外圧)を伴うものだと、私は考えています。
ベンチャー企業で、右も左も分からないまま、訳も分からず営業の最前線に放り込まれた1年目、2年目の頃を思い返すと、あのレベルの業務量と精神的なプレッシャーは、到底「自分の成長のため!」というポジティブな意欲だけで乗り切れるものではありませんでした。
「いつ怒鳴られるか」「いつクレームになるか」…常にそんな恐怖と隣り合わせで、ただ必死に目の前のタスクをこなすしかなかったのです。
「セルフ激務」も、もちろん大変です。しかし、そこには「自分で選んでいる」「自分のペースで調整できる」という側面が、少なからずあります。しかし、「やらされ激務」には、その選択肢すらありません。この「自己決定権の有無」が、両者を分ける決定的な違いなのです。
「激務」経験のメリット・デメリットを徹底解剖
では、この(主に「やらされ」型の)激務を経験することには、一体どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか? 私は、これを「マインド(精神面)」と「能力・スキル面」の二つの側面から分けて考えるべきだと思っています。
【メリット】① マインド面
「恐怖」がなくなり、「胆力」がつく 激務経験の最大のメリットは、間違いなくこのマインド面での成長にある、と私は断言します。
20代で社会に出たばかりの頃というのは、誰しもが「自分はこの会社でやっていけるだろうか?」「仕事で成果を出せるだろうか?」といった「不安」や「焦り」、「失敗したらどうしよう」という「恐怖」、そして周囲からの期待や評価に対する「プレッシャー」に晒(さら)されますよね。
特に、お客様からクレームを受けたり、厳しい要求を突きつけられたり、あるいは社内で理不尽な叱責を受けたり…といった経験は、心を大きく揺さぶります。こうしたストレスフルな状況に、どう対処し、乗り越えていくか。いわば、社会を生き抜くための「メンタルの強さ」「打たれ強さ」が求められるわけです。
そして、「やらされ激務」のような、自分の意志ではコントロールできないレベルの圧倒的な外圧に長期間さらされる経験は、このメンタル面を、ある意味「強制的に」鍛え上げる効果があるのです。
簡単に言えば、「恐怖」に対する感覚が麻痺(まひ)していく、あるいは「耐性」が上がる、ということです。一度、想像を絶するような修羅場を経験してしまうと、それ以降に起こる大概の困難は、「まあ、あの時に比べれば…」と、相対的に小さく感じられるようになります。
例えば、転職活動の面接で、「うちの会社は、正直言ってかなり厳しい環境ですよ。ついてこれますか?」と脅しのようなことを言われたとします。激務経験がない人なら、「えっ、大丈夫かな…」と不安になるかもしれません。しかし、「やらされ激務」を乗り越えてきた人は、「は? 全然余裕ですけど、何か?」と思えてしまいます。
口には出しませんが、内心ではそう感じられるだけの「胆力(たんりょく)」が身についているのです。 これは、単なる「強がり」ではありません。根拠のない自信ではなく、「どんな厳しい状況に置かれても、自分なら何とかやっていけるだろう」という、経験に裏打ちされた自己効力感(じここうりょくかん)のようなものです。
どんな手強い相手が出てこようが、どんな理不尽なことを言われようが、どんな逆境に立たされようが、「まあ、死ぬわけじゃないし、何とかなるだろう」と、腹を括(くく)れる強さ。これが、激務経験がもたらす、最大の「果実」だと私は考えています。
【デメリット】② 能力・スキル面
一方で、「激務を経験すれば、仕事の能力やスキルが飛躍的に向上するか?」と問われると、私は「必ずしもそうとは言えない、むしろ逆効果の場合もある」と考えています。
なぜなら、激務の渦中にいる時というのは、肉体的にも精神的にも、常に限界ギリギリの状態です。例えるなら、CPUが常に100%稼働し、オーバーヒート寸前のパソコンのようなもの。
そんな状態で、冷静に物事を考えたり、新しい知識を吸収したり、ましてや自分の仕事を客観的に振り返って改善点を見つけたりする「精神的な余裕(よゆう)」は、ほとんどありません。 ただただ、目の前のタスクをこなすことに追われ、「やらされ感」の中で、思考停止に陥ってしまう。これが、激務下におけるリアルな状況ではないでしょうか。
能力やスキルを本当に伸ばそうと思ったら、やはり、ある程度の「余裕」が必要です。
「昨日のあのお客様への提案、もっとこういう言い方があったんじゃないか?」
「この業務プロセス、もっと効率化できないだろうか?」
「自分の営業スタイルを、今後どう進化させていこうか?」
…といった「内省(ないせい)」や「学習」のための時間と精神的な余白があって初めて、人は成長できるのです。激務の中では、残念ながら、その余裕が奪われてしまいがちです。
私が以前在籍していた、人材系のブラックベンチャー企業(4年間営業職として勤務しました)を辞めた元同僚たちに、「あの会社で働いて、一番良かったことは何?」と聞いても、おそらく誰一人として、「人材業界に関する深い専門知識が身についた」とか、「高度な営業テクニックや交渉術を学べた」とは答えないでしょう。
彼らが口を揃えて言うのは、 おそらく「いやー、とにかくキツかった。何度も心が折れそうになった。でも、あの経験のおかげで、たいていのことでは動じなくなった。怖いものがなくなった」と。 つまり、彼らが得たのは、やはり「スキル」ではなく、「マインド(胆力)」だったわけです。
なぜ、年配者は「激務はやった方がいい」と言うのか? この「マインド面での成長」こそが、今の40代〜60代くらいの世代が、若者に対して「若いうちに激務を経験しておけ」「苦労は買ってでもしろ」と言う、その「真意」なのではないか、と私は推測しています。
もちろん、彼らの言い分は、時に「昔はこうだった」というノスタルジーや、「自分たちが苦労したんだから、お前たちも苦労しろ」という、やや乱暴な精神論に聞こえることもあります。
激務を経験したからといって、必ずしも仕事ができるようになるわけではありません。そこは、明確に分けて考えるべきです。
しかし、彼らが言いたいのは、おそらくこういうことではないでしょうか。
「世の中には、能力やスキルは十分にあるのに、『不安』や『恐怖』といったマインド面でのつまずきによって、自分の可能性を狭めてしまっている人が、あまりにも多い」
「外圧への耐性が弱すぎると、『ここが怖いから行けない』『失敗したらどうしよう』という気持ちが先に立ち、挑戦すべき場面で一歩を踏み出せず、安全な『迂回(うかい)ルート』ばかりを選んでしまう。それでは、大きな成長は望めないぞ」と。
しかも、厄介なことに、当の本人は、自分が「迂回ルート」を歩んでいることにすら、気づいていないケースが多いのです。
営業で例えるなら、本当は「新規の飛び込み営業」に挑戦すれば、もっと大きな成果を出せる可能性があるのに、「飛び込みなんて怖い」「断られるのが嫌だ」という恐怖心から、その選択肢を無意識のうちに排除してしまう。
そして、既存顧客からの紹介や問い合わせ(引き合い)といった、比較的安全なルートだけで営業活動を行い、「自分なりに頑張っている」「これ以上、売上を伸ばす方法はない」と思い込んでしまう…。 これは、非常にもったいないことです。
能力やスキルという「武器」は持っているのに、それを振るうための「勇気(恐怖心のなさ)」が足りないために、宝の持ち腐れになっている状態です。
激務経験によって得られる「外圧耐性」や「胆力」は、こうしたマインド面での「見えない壁」を取り払い、より大胆な挑戦を可能にする、いわば「心のアクセル」のような役割を果たすのかもしれません。
年配の方々が「激務はやった方がいい」と言う背景には、こうした経験則があるのではないでしょうか。
要注意!「意味のない激務」も存在する
ただし、ここで一つ、非常に重要な注意点があります。それは、「すべての激務に意味があるわけではない」ということです。 激務を、単に「長時間、厳しいプレッシャーの中で働くこと」と一括(ひとくく)りにしてしまうのは危険です。「意味のある激務」と「意味のない激務」を、きちんと見極める必要があります。
私が経験した「意味のない激務」の典型例を、いくつかご紹介しましょう。
「あの気難しい課長に睨(にら)まれないように、日報のこの部分を、もっともらしく、かつ無難に書き直さないと…」(深夜まで続く、作文作業)
「この社内プレゼン資料、〇〇部長への忖度(そんたく)が足りないって言われないように、『〇〇部長並びに関係各位への感謝』のページを、もっと分厚くしないと…」(パワポ職人と化す週末)
「とにかく会議の数だけは多いけど、中身は毎回同じことの繰り返し。でも、欠席すると『やる気がない』と思われるから、とりあえず全部出ないと…」(思考停止の長時間拘束)
…いかがでしょうか? これらは、客観的に見れば、明らかに「時間の無駄」であり、会社の生産性にも、個人の成長にも、何一つ貢献しない、くだらない社内政治や形式主義が生み出した「激務」です。
こういった「意味のない激務」は、どれだけ経験しても、激務本来のメリットであるはずの「恐怖がなくなる」「胆力がつく」といったマインド面の成長には、全く繋がりません。
むしろ、精神をすり減らし、「会社って、くだらないな…」という無力感や皮肉な考えを植え付けるだけです。
後から振り返っても、「あの時間は、一体何だったんだ…」と、虚しさが込み上げてくるばかりです。 ですから、「激務賛成派」の中年世代の中にも、二種類の人間がいると考えるべきです。
適切な目的を持った「意味のある激務」(例えば、困難なプロジェクトの達成、厳しい顧客折衝、新規事業の立ち上げなど)を経験し、その結果として「恐怖心」がなくなり、胆力がついた人。
上記のような「意味のない激務」(社内政治、形式主義、非効率な長時間労働など)を経験し、それを「苦労」だと勘違いしている人。
当然、この両者では、「激務」に対する考え方や、若者へのアドバイスの内容も、全く異なってくるはずです。
もし、あなたの周りに「激務はやった方がいい」と主張する人がいたら、その人が経験してきた「激務」が、果たしてどちらのタイプだったのか、少し冷静に見極める必要があるかもしれません。
「マインド」で道を切り拓く、という生き方
もう一つ、「激務賛成派」に多いパターンとして、「マインドで道を切り拓(ひら)いてきた」タイプの人がいます。 先ほど述べたように、激務は、能力やスキルを直接的に伸ばす上では、必ずしも最適な環境とは言えません。
しかし、激務時代に培った「外圧耐性」「恐怖心のなさ」「胆力」といった強靭(きょうじん)なマインドを武器にして、未知の領域に飛び込み、困難な挑戦を乗り越え、結果的に成功を掴(つか)んできた、という人たちが、確かに存在するのです。
例えば、全くの未経験の業界に営業職として飛び込んだり、会社を辞めて独立・起業したり、あるいは、誰もやったことのない新しいセールス手法を開発したり…。これらの挑戦には、既存の能力やスキルだけでは足りない部分が必ず出てきます。
そんな時、最後の拠り所となるのが、「なんとかなるだろう」「失敗しても、また立ち上がればいい」という、折れない心、恐れないマインドなのです。
このルートで成功体験を積み重ねてきた人は、「あの激務の経験があったからこそ、今の自分があるんだ」と、肌感覚で強く実感しているはずです。
何を隠そう、私自身も、どちらかというと、この「マインド開拓型」のキャリアを歩んできたという自覚があります。
だからこそ、激務経験がもたらす「恐怖がなくなる」というメリットの大きさを、身をもって感じているのです。そういう意味では、私も「激務賛成派」に近いのかもしれません。
世の中には、様々な成功への道があります。圧倒的な能力やスキルで道を切り拓く人もいれば、卓越した人脈やコミュニケーション能力で成功する人もいるでしょう。
しかし、「恐怖を感じない」という強靭なマインドもまた、人生の選択肢を大きく広げ、道を切り拓くための、非常に強力な武器になり得る、ということを、私は自身の経験から確信しています。
「激務を肯定する人」の中には、こうした「マインド開拓型」の成功体験を持つ人が、少なからずいるのではないでしょうか。
経営者から見た「激務経験」の価値とは?
最後に、経営者という視点から、「激務経験」の価値について考えてみましょう。
会社を経営するということは、日々、予期せぬ困難や課題との戦いです。売上が急に落ち込んだり、重要な取引先を失ったり、頼りにしていた社員が突然辞めてしまったり…。常に、高いプレッシャーと不確実性の中で、孤独な決断を下し続けなければなりません。
そんな時、若い頃に「やらされ激務」のような修羅場を経験していると、「まあ、あの時に比べれば、まだマシだ」「どんな状況でも、何とかするしかない」という、ある種の「覚悟」や「基本的な自信」を持つことができます。
パニックに陥らず、冷静に状況を分析し、次の一手を打つための、精神的な「土台」ができているのです。これは、経営者にとって、非常に大きなアドバンテージとなり得ます。
これは、トップクラスの営業にも共通して言えることかもしれません。彼らの多くは、過去の厳しい営業経験を通じて培われた、「どんな逆境でも諦めずに前に進む力」「プレッシャーを楽しむくらいの胆力」を持っているように見受けられます。
ただし、もちろん、経営や営業において、精神力だけで全てが解決するわけではありません。会社を成長させ、継続的に成果を出し続けるためには、激務経験から得た「恐れない心」に加えて、冷静な「戦略的思考力」や「分析力」、そして市場や顧客の変化に対応する「学習能力」が不可欠です。
重要なのは、激務経験によって培われた「マインド(胆力)」と、(激務ではない)少し余裕のある環境で意識的に磨かれた「能力・スキル(戦略的思考力や学習能力)」との、バランスなのです。どちらか一方だけでは、長期的な成功は難しいでしょう。
まとめ:あなたのキャリアにとって、「激務」とは何か?
さて、「激務は経験すべきか?」という問いに戻りましょう。 この問いに対する、唯一の「正解」はありません。答えは、あなたがどんなキャリアを目指し、どんな人生を送りたいかによって、変わってくるはずです。
しかし、私の経験と考察から、以下の点は言えるかと思います。
激務経験の最大の価値は、「スキルアップ」ではなく「マインド面での成長(恐怖心がなくなり、胆力がつくこと)」にある。
能力やスキルを効率的に伸ばしたいのであれば、激務ではない、少し余裕のある環境の方が適している。
全ての激務に価値があるわけではない。社内政治や形式主義から生まれる「意味のない激務」は、百害あって一利なし。見極めが重要。
激務で培われた「恐れない心」は、営業職や経営者として、未知の領域に挑戦し、道を切り拓く上で、非常に大きな武器になり得る。
最終的に重要なのは、「激務か、そうでないか」という単純な二元論ではありません。自分のキャリアのどの段階で、どのような種類の「激務(あるいは挑戦)」を経験し、そこから何を学び、どう活かしていくか、という視点です。
営業として、あるいは経営者として、より高いレベルを目指すのであれば、時には厳しい状況やプレッシャー(それが「激務」と呼ばれるものかもしれません)を、恐れずに受け入れ、乗り越えていく「勇気」と、その経験から学びを得て次に活かす「知恵」の両方が必要になるのではないでしょうか。
「若手時代の激務経験を、今の経営やマネジメントにどう活かせばいいか?」「部下に『意味のある挑戦』を促すにはどうすればいいか?」など、具体的なお悩みがあれば、ぜひご相談ください。 まずは、60分間の無料オンライン相談で、あなたの悩みや目指したい姿をお聞かせください。無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。よろしければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。
あなたのキャリアにとって、「激務」とは、どんな意味を持つでしょうか? 一度、じっくりと考えてみる価値はあるかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。