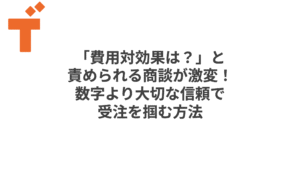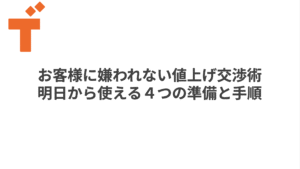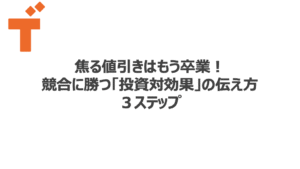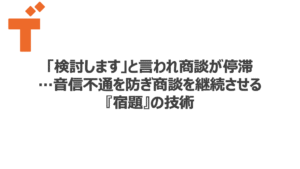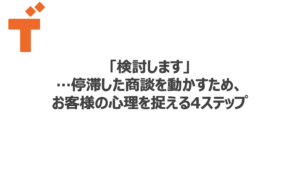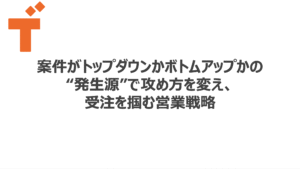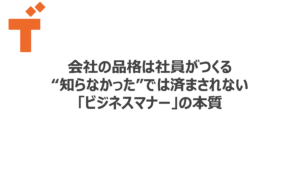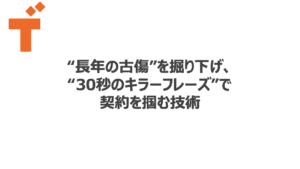営業への進捗確認は、「受注の時期」ではなく「受注決定の場面」を掴むこと
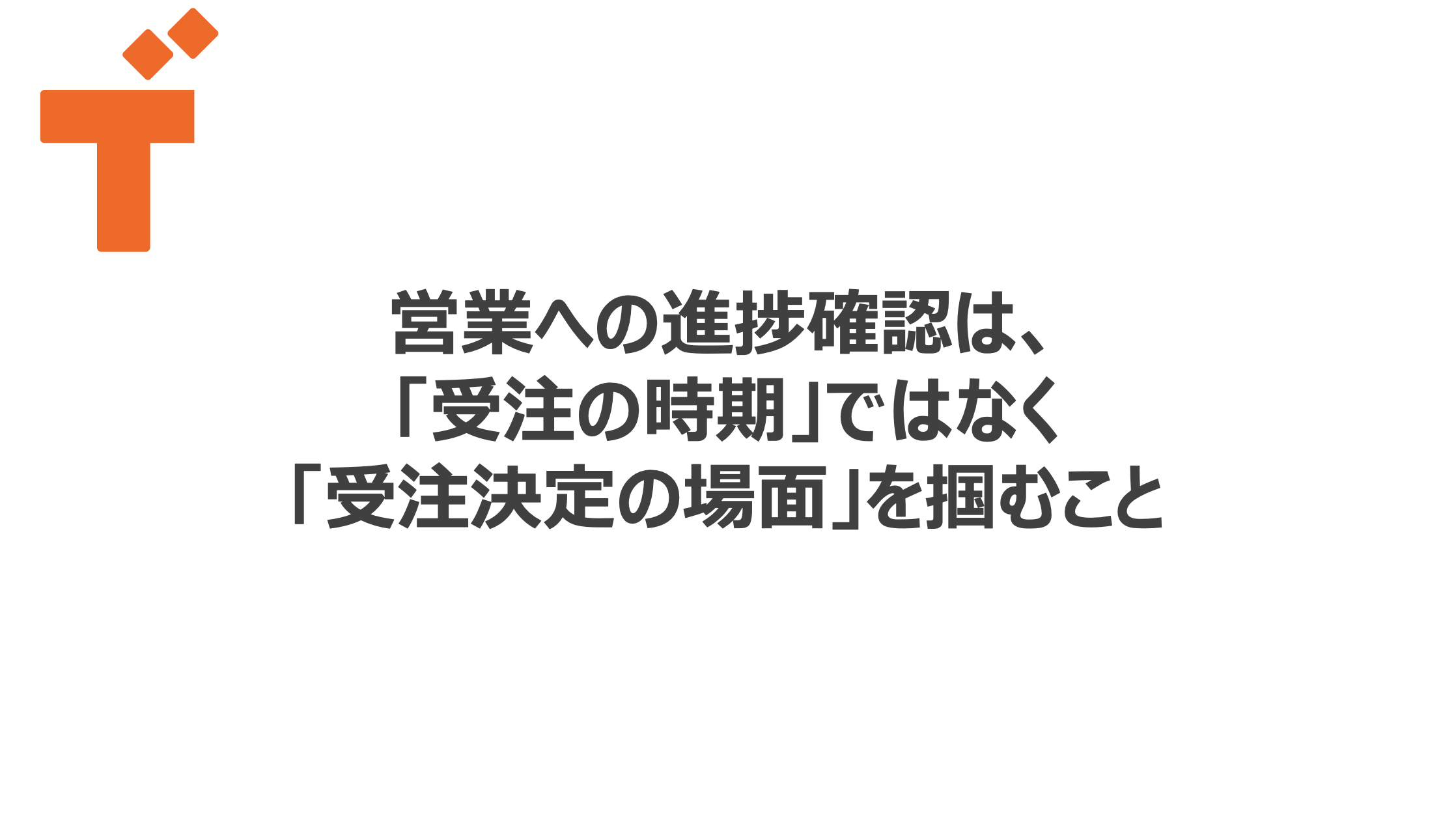
「A社の案件だけど、これ、いつ決まるんだっけ?」
「えーっと、先週の感触だと、今週中にはお返事いただける“はず”なんですけど…」
経営者や営業マネジャーの皆さま。 あなたの会社の営業会議で、毎週のようにこんなやり取りが繰り返されていませんか?
案件の一覧を見ながら、「いつ決まる?」と確認し、「〜〜はずです」という曖EMC(あいまい)な返事を聞く。そして、「早く連絡してよ!」と指示を出す…。
もし、そんな“報告待ち”の営業管理が常態化しているとしたら、非常に危険なサインです。それは、チームがお客様の状況を正確に掴めていない何よりの証拠だからです。
この記事を読めば、なぜ「いつ決まる?」と聞くマネジメントが売上を遠ざけるのか、その根本的な理由がわかります。
そして、「時期」という曖昧なものではなく、受注が決まる「決定的な場面」を掴み、契約率を劇的に上げるための、明日から使える具体的な営業管理術が手に入ります。
なぜ営業会議の進捗確認は、「希望的観測」の場になるのか
月曜、朝9時。 重たい空気の中、営業会議が始まります。 モニターには、案件管理リスト(パイプライン)が映し出されています。
マネジャー:「B社のこの案件、今週が『受注決定予定日』になってるけど、状況はどう?」
メンバー:「はい。先方の担当者からは、『すごく前向きに進めてます』と聞いています。なので、今週中には良いお返事をいただける“はず”です」
マネジャー:「“はず”じゃ困るんだよ。確度はどうなんだ? 本当に今週決まるんだろうな?」
メンバー:「(うわぁ、まただ…『前向きです』としか言われてないのに、どう答えろと…)ええ、感触としては、80%くらいかと…」
マネジャー:「分かった。じゃあ、今週の売上見込みに入れておくぞ。もし遅れそうなら、すぐ催促の連絡を入れろよ!」
メンバー:「(『どうなりましたか?』なんて催促の電話、一番やりたくないんだよな…)…はい、分かりました」
…いかがでしょうか。 日本中の多くの会社で、このような光景が繰り広げられています。 しかし、この会話には、受注を掴むための「戦略」が1ミリも含まれていません。
マネジャーが確認しているのは、単なる「日付(時期)」だけ。 メンバーが答えているのは、根拠のない「感触」と「希望的観測」だけ。
これでは、営業担当者の精神的なプレッシャーが増すだけで、受注率は絶対に上がりません。それどころか、「〜〜のはず」という曖昧な情報がチーム全体の数字の読みを狂わせ、経営者の立てる事業計画そのものを危うくしてしまうのです。
この負のループから抜け出すために、私たちはまず、「何を管理すべきか」という“モノサシ”そのものを変える必要があります。
「いつ決まる?」を撲滅せよ! 売上を劇的に変える「3つの新常識」
受注率の高い営業チームは、「いつ決まるか(時期)」を追いかけません。 彼らが徹底的に追いかけているのは、**「“何をもって”決まるか(場面)」**です。 この決定的な違いを生み出す、3つの新常識をご紹介します。
新常識①:追うべきは「日付」ではなく「場面」
結論: 「受注決定予定日」という“日付”の確認を、今すぐやめましょう。
理由: 「今週中」「今月中」といった曖昧な「時期」の概念は、お客様と営業の間で「契約する」という具体的なイメージが共有できていない証拠だからです。
一歩目: マネジャーはメンバーに「いつ決まる?」と聞く代わりに、「その案件、“何をもって”決まることになってる?」と質問を変えてください。
なぜ「時期」を追うと失敗するのか
「今週中にお願いします」「今月中にやります」といった会話は、普段のビジネスシーンでは当たり前に使われます。社内のタスク管理なら、それでも問題ないかもしれません。
しかし、こと「営業マネジメント」においては、この「時期」という概念は、最も排除すべき言葉です。
なぜなら、お客様が発する「今週中には…」は、多くの場合、何の約束もしていないからです。それは単なる「目標」や「願望」であり、営業が期待していい「合意」ではありません。
本当にフォーカスすべきは、「最後、契約が決まる瞬間(=場面)」を、お客様と営業担当者の両方が、どれだけ具体的にイメージできているか、という一点に尽きます。
「いつですか?」と時間(点)で聞くから、相手も「今週中です」と時間(幅)でしか答えられないのです。
そうではなく、「どのような“場面”で決まりますか?」と聞くのです。 すると、お客様の頭の中にある「プロセス」が見えてきます。
「ああ、それはね、来週の経営会議にかけるんだよ」
「いや、会議とかじゃなくて、俺(担当者)が稟議書(りんぎしょ=社内を通すための書類)を書いて、部長のハンコがもらえれば決まるよ」
ほら、これだけで、「今週中」という曖昧な言葉よりも、はるかに具体的で、次に何をすべきかが明確になったと思いませんか? 営業マネジメントとは、単なる「時期」の確認ではなく、この「決まる場面」を特定し、そこから逆算して行動を設計することなのです。
新常識②:「決まる場面」を2パターンで解像度を上げる
結論: お客様の「決まる場面」は、突き詰めれば「会議」か「個人の決断」の2パターンしかありません。
理由: この2パターンを具体的に想定することで、営業が次に取るべきアクション(誰に・何を・いつまでに提供すべきか)が、自動的に決まるからです。
一歩目: お客様に「最終的に決まるのは、会議の場でしょうか? それとも、どなたかお一人のご判断でしょうか?」とストレートに確認してみましょう。
「場面」を特定した後の、具体的な営業戦略
「場面」さえ特定できれば、営業がやるべきことはシンプルです。「いつ決まる?」と不安に思いながら“待つ”営業から、「その場面で確実に決めてもらう」ための“準備”をする営業へと変貌できます。
パターンA:「会議」で決まる場合
お客様から「来週の役員会議で決まります」という情報を引き出せたとします。 ここで「そうですか、では良いお返事をお待ちしてます!」と引き下がっては、三流の営業です。 一流の営業マネジャーは、メンバーにこう確認させます。
- 「その会議は、そもそもどういう位置づけの会議ですか?」 (例:投資判断をするためだけの特別な会議ですか? それとも、毎週やっている定例会議の中の、議題の一つとして扱われるのですか?)
- 「その会議には、どなたが参加されますか?」
- 「会議では、どのような資料(当社の提案書など)が使われますか?」
- 「その資料は、どなたが準備されるのですか? 私たちにお手伝いできることはありませんか?」
ここまで聞けば、もうお分かりですね。 これは「時期」の話ではなく、完全に「プロセス」の話です。
もし定例会議の議題の一つとして扱われるなら、議論の時間は15分程度かもしれません。その短い時間で決めてもらうには、一目でメリットが分かる“まとめ資料”が別途必要かもしれません。
もし、お客様の担当者が資料を作るなら、営業は「その会議で出そうな反対意見」を想定し、それに対する「切り返しトーク」をまとめた“想定問答集”を作ってあげるべきです。
「会議」という場面が分かれば、やるべき準備が無限に見えてきます。
パターンB:「特定の人物(キーパーソン)」が1人で決める場合
次に、「会議ではなく、ウチは部長のAさんが決めます」という情報を得たとします。 ここでも「Aさんによろしくお伝えください!」では、仕事をしたことになりません。
一流の営業マネジャーは、さらにこう深掘りさせます。
- 「そのA部長は、これまでの打ち合わせに参加されていましたか?」 (=当社の情報をすでに十分に持っているか?)
- 「もし参加されていない場合、どなたが、A部長に情報を共有されるのですか?」 (=担当者であるあなたが、稟議書(りんぎしょ)などで説明するのですか?)
もし、A部長がこれまでの経緯を全く知らず、担当者からの情報共有(稟議書など)だけで判断する場合、どうでしょうか? その「稟議書」の出来次第で、結果が全て決まってしまいます。
ならば、営業がやるべきことは一つです。「A部長が決裁しやすいように、稟議書の叩き台(たたきだい=元になる案)を、私たちが一緒に作りますよ!」と提案することです。
投資対効果の計算、導入する理由、他社ではなく御社を選ぶ理由…それらを完璧なロジックで組み立てた資料を提供するのです。
どちらのパターンでも同じです。 「決まる場面」と「そこに至るプロセス」を具体的にイメージし、お客様と共有し、合意する。 これができれば、「いつ決まるんだろう…」という不安な“待ち”の状態は消え失せ、契約に向けた具体的な“共同作業”が始まるのです。
新常識③:受注の「生データ(場面)」を組織の最強資産にする
結論:受注が決まった「場面」の生々しい情報を集め、社内で徹底的に共有しましょう。
理由: この「場面」の解像度が組織の文化になれば、「時期」で考える営業がいなくなり、チーム全体の受注率が底上げされるからです。
一歩目: まずは受注したお客様1社に、「(今後のために)今回、どのような『場面』で決めていただけたのか」を具体的にヒアリングしてみましょう。
どうやって「場面」を共有する文化を作るか
とはいえ、これまで「時期」で管理してきた組織が、急に「場面」で考えろと言われても、戸惑うかもしれません。 この新しい文化を組織に根付かせるための、具体的な方法を2つご紹介します。
方法1:エース営業マンの「頭の中」を解き明かす
あなたの会社にいる、トップ営業マンを思い浮かべてください。 彼ら・彼女らは、おそらく無意識のうちに、この「場面」を掴む作業をやっています。だから、お客様の状況を正確に把握し、高い受注率を叩き出せるのです。
しかし、彼らはその詳細なプロセスを、営業会議でわざわざ報告していないケースがほとんどです。 「B社、決まりました」「どうやって決めたんだ?」「いや、まあ、うまくやりました」…これでは、他のメンバーの学びになりません。
経営者やマネジャーであるあなたの仕事は、そのトップ営業マンに、「先日受注した案件は、具体的にどういう“場面”で決まったのか」を、他のメンバーの前で詳細に話させることです。
- 「何月何日、何時から行われた、〇〇という名前の会議で決まりました」
- 「参加者は、A部長とB課長と、現場のCさんでした」「会議では、私が作ったこの3枚の“まとめ資料”が使われました」
- 「会議中、B課長から『コストが高いのでは?』という意見が出ましたが、Cさんが『いや、この機能がないと現場が困る』と助け舟を出してくれました」
- 「最終的に、A部長が『よし、Cさんがそこまで言うなら、やろう』という、このセリフで決まりました」
どうでしょうか。 ここまで生々しい「場面」の情報を共有すれば、他の営業メンバーは「なるほど、現場のCさんを味方につけておくことが、A部長の最後の決断に効いたのか」と、具体的なノウハウとして学ぶことができます。
方法2:受注直後の「お客様ヒアリング」を仕組み化する(こちらがオススメ!)
方法1はトップ営業マンの能力に依存しますが、もっと簡単な方法があります。 それは、お客様に直接聞いてしまうことです。
法人営業(BtoB)において、お客様が「発注します」と決めた直後は、その営業担当者や会社に対する「期待」が最も高まっているゴールデンタイムです。
「さあ、いよいよお願いしますよ!」「御社に決めてよかったです!」 お客様は、こういうポジティブな心理状態にあります。
このタイミングを逃さず、例えばカスタマーサクセス(導入支援)や納品のキックオフミーティングの冒頭で、このように切り出します。
「この度は、ご発注いただき誠にありがとうございます。ぜひ御社の期待に応えていきたいと思いますので、差し支えなければ、一つだけお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「今回、最終的にどのような経緯で、当社に決めていただけたのでしょうか? おそらく、社内で色々なご議論や、〇〇様(担当者)の中でも葛藤があったかと思います」
「その『決まった場面』の背景を我々が深く理解しておくことが、御社が何を求めていらっしゃるかを正確に把握し、期待に応えやすくなる一番の近道だと考えております。覚えていらっしゃる範囲で、ぜひお聞かせいただけませんか?」
(※セリフは、あなたの会社の商材に合わせてアレンジしてください)
期待値が最高潮のお客様は、多くの場合、その「社内ドラマ」を喜んで話してくれます。 「いやー、実はね、先週の会議で…」 「部長が最後まで渋ってたんだけど、〇〇さんがね…」
この貴重な話を、オンライン会議なら録画させてもらいましょう。(もちろん、「記録のために録画してもよろしいですか?」と許可を得てください) 対面であれば、その場で話されたセリフをそのままメモ(議事録)に残します。
この「場面に関する生データ」を社内に蓄積し、共有するのです。 これが数件溜まってきたら、組織はどうなるでしょうか?
「A社みたいなパターンは、会議で現場のキーパーソンが発言すると決まるな」
「B社みたいなパターンは、部長個人が決めるから、稟議書のロジックが命だな」
このように、組織全体で「どのようにして案件が決まるのか」についての理解が深まっていきます。 そうなれば、上層部(経営者やマネジャー)も、単なる「時期」ではなく、この本質的な「場面」にフォーカスしたマネジメントをしたいと自然に思うようになるはずです。
まずは、次の営業会議で「質問」を変えてみよう
「あの案件、いつ決まる?」 この、営業担当者を追い詰めるだけで、何も生み出さない魔法の言葉。 明日から、その言葉を封印してみませんか?
経営者や営業マネジャーであるあなたが、今日からできる「一歩目」は、非常にシンプルです。
次に開く営業会議で、メンバーにかける「質問」を一つだけ変えてみてください。
「いつ決まる?」と聞く代わりに、「その案件、決まる“場面”を一緒に想像してみようか。会議で決まる? それとも、誰か特定の一人が決める?」 と、問いかけてみましょう。
その一言が、曖昧な「期待」を具体的な「戦略」に変え、チームの空気を変え、そして会社の売上を安定させる、確実な第一歩となるはずです。
“待ち”の営業文化を、“決める”営業文化に変えませんか
あなたの会社の営業チームは、「いつ返事が来るか」を待つ“受け身”の集団になっていませんか? そうではなく、お客様の「決定プロセス」に深く寄り添い、「この“場面”で決めてもらう」と設計できる“攻め”の営業集団へと変革させたいとは思いませんか?
もし、
- 「いつ決まる?」という曖昧な会議を、具体的な戦略会議に変えたい…
- 勘や根性論ではなく、お客様の「決定場面」を掴む論理的な営業チームを作りたい…
- “待ち”のストレスから営業担当者を解放し、安定的に売上を積み上げたい…
と、本気でお考えの経営者・営業マネジャーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
トレテクでは、単なるセールストークの研修ではなく、「受注が決まる場面」をいかに設計し、お客様と合意し、確実に契約へと導くかという、本質的な営業マネジメントの導入をサポートします。
まずは、60分間の無料オンライン相談で、貴社が今抱えている営業の課題や、「どうなったら理想か」という未来像を、気軽にお聞かせください。無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。
下記のリンクから、今すぐお申し込みいただけます。
▶︎▶︎60分無料オンライン相談はこちらから◀︎◀︎
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。こちらもぜひフォローして、貴社の営業力強化にお役立てください。
あなたの会社の営業が、お客様から心から信頼され、「あなただから決めた」と言われる存在になるためのお手伝いができることを、楽しみにしています。 最後までお読みいただき、ありがとうございました