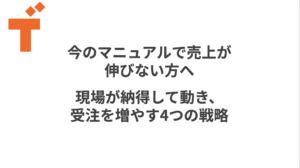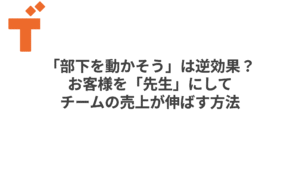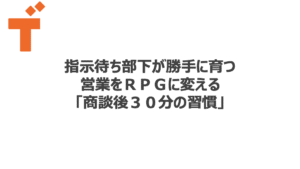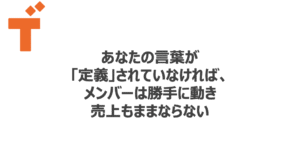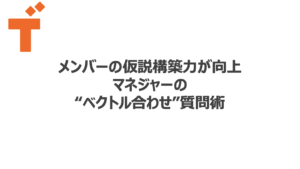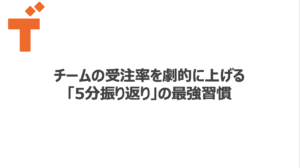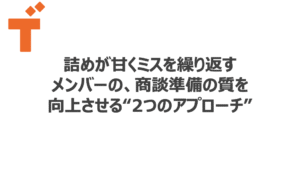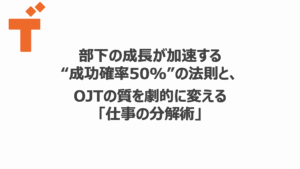「自分で考えろ」はリスクある投げかけ 自律的な営業を育成するためには
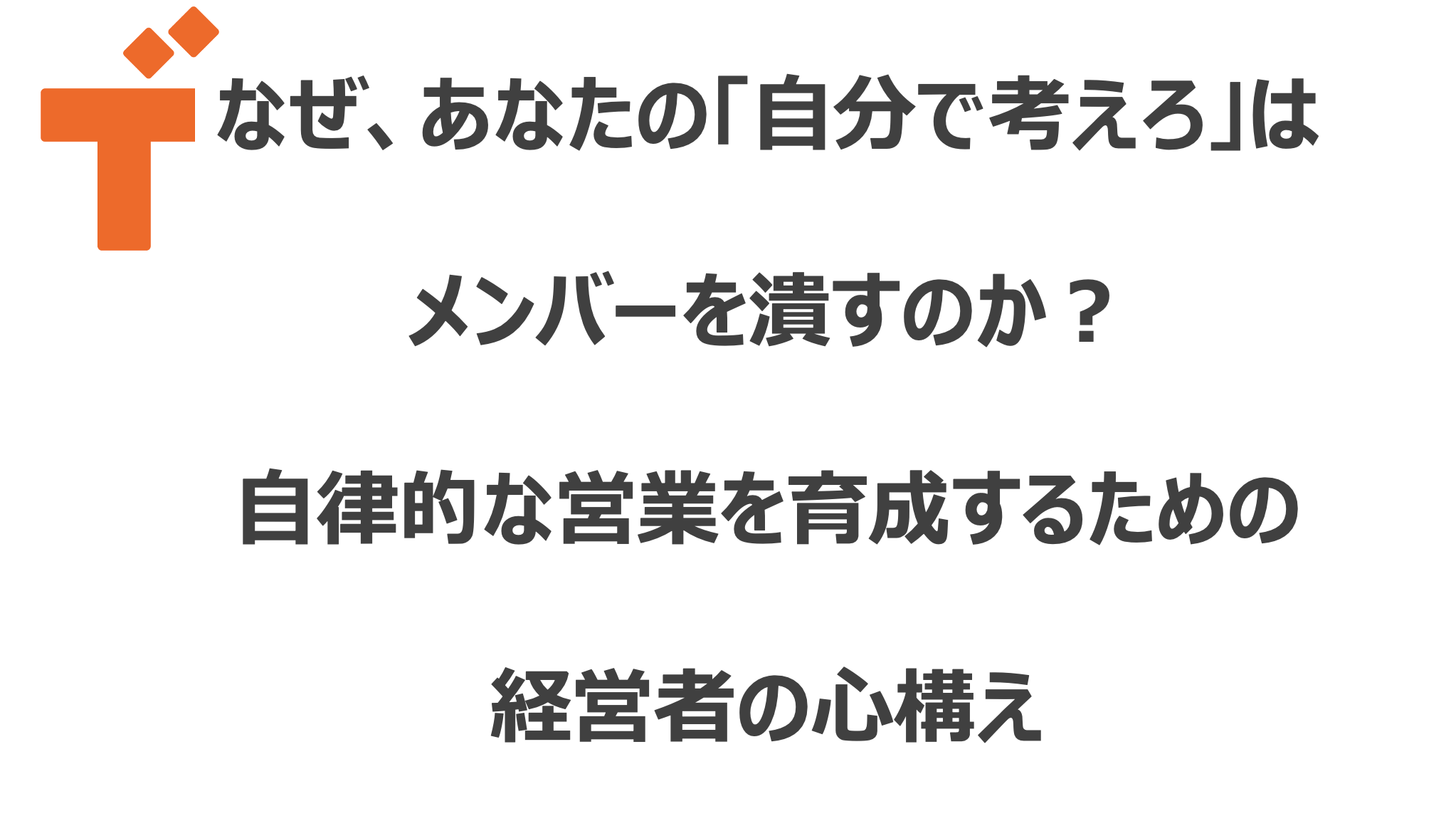
「いつまで経っても部下が育たない…」
「『自分で考えろ』と伝えているのに、思考停止してしまう…」
「結局、自分がやった方が早い、と仕事を抱え込んでしまう…」
経営者として、あるいは営業マネジャーとして、部下の育成に関するこんな悩みを抱えてはいませんか?
成長を促すために投げかけたはずの「自分で考えろ」という言葉。それが、意図とは裏腹に、部下の心を閉ざし、成長を妨げ、チーム全体の売上停滞の原因にさえなっているとしたら…。
この記事では、その一言が「成長を促す劇薬」にも「可能性を潰す毒」にもなり得る理由を徹底的に解き明かします。
そして、部下一人ひとりが自律的に考え、行動し、粘り強く契約を獲得できるような、本当に強い営業チームを作るための、育成の本質について深く掘り下げていきます。
貴社の営業力を飛躍させる「実践型」コンサルタント
ベンチャー・大企業合わせて約20年以上営業現場経験を武器に、貴社に再現性のある「売れる仕組み」を構築します。
現在も営業職として現場の泥臭さを経験しているからこその営業視点を強みとして、座学研修のほか、今日からすぐに使える実践的なノウハウで、特に商談・プレゼン力の向上に貢献します。
「売上を伸ばしたいが、何から手をつければ…」とお悩みの経営者・営業部長様へ、実践型コンサルティングで、貴社の営業チームを強化し、確かな成果へと導きます。

「良かれと思って」が、なぜか裏目に出る…育成現場の“すれ違い”
若手や新人の営業担当者から、次々と質問が飛んでくる。「〇〇社の件、どうしましょうか?」「この資料、これでいいですか?」「次、何をすればいいですか?」
最初は丁寧に教えていたものの、いつまでも同じような質問が続くと、さすがに痺れを切らしてしまう。「それくらい、いい加減自分で考えてくれよ」と。そして、相手の成長を願う気持ちも込めて、少し突き放すように、こう告げるのです。
「一度、自分で考えてみて」
こちらとしては、いつまでも指示待ち人間でいてほしくない、自分自身の頭で考え、乗り越える力をつけてほしい、という親心にも似た気持ちからの言葉です。
しかし、その言葉を受け取った部下の表情は、どこか曇っています。そして、その日を境に、彼(彼女)からの質問はパタリと止んでしまう。
「お、やっと自分で考えるようになったか」と一瞬安堵したのも束の間、数週間後、その部下が担当していた案件で大きなトラブルが発覚。
「どうして、もっと早く相談しなかったんだ!」と問い詰めると、部下は俯いたまま、か細い声でこう呟くのです。
「…自分で考えろ、と言われたので…」
良かれと思って与えた「考える機会」が、相手にとっては「相談してはいけない」というメッセージ、あるいは「指導放棄」「丸投げ」と受け取られてしまっていた。
この、なんともやるせないすれ違い。こうした経験に、心当たりのある経営者やマネジャーの方は、決して少なくないのではないでしょうか。
このコミュニケーションの断絶は、単に気まずい雰囲気を生むだけでなく、ミスによる損失や機会損失を招き、ひいてはチーム全体の売上や契約件数に、深刻なダメージを与えかねない、非常に根深い問題なのです。
今回は、私の経験から見出した「自分で考えろ」という言葉を、部下を潰す“呪いの言葉”ではなく、そのポテンシャルを最大限に引き出す“魔法の言葉”に変えるための、具体的な方法論をお伝えしたいと思います。
すべての元凶は「分類」の欠如にある
なぜ、「自分で考えろ」という指導は、うまくいったり、いかなかったりするのでしょうか? なぜ、ある人には成長のきっかけとなり、ある人には心を折る一撃となってしまうのでしょうか?
その答えは、非常にシンプルです。それは、指導者が「仕事の種類」を正しく分類できていないからです。
私たちの目の前にある仕事は、大きく分けて2つの種類に分類できます。これこそが、効果的な育成のすべての出発点となります。
- 「正解」が明確に決まっている仕事
- 「正解」が決まっていない仕事
まず、この2つの違いについて、深く理解することから始めましょう。
1.「正解が決まっている仕事」は、さっさと教えなさい
まず、一つ目の「正解が明確に決まっている仕事」。これは、誰がやっても、いつやっても、答えが一つしかないような種類のタスクです。
例えば、「パソコンでこのデータを印刷する方法」「経費精算システムの申請手順」「自社の製品Aの標準価格」「社内の〇〇さんに内線をかける方法」など。これらは、手順やルール、事実に基づいたものであり、個人の解釈や工夫が入り込む余地はほとんどありません。
こうした「正解が決まっていること」について、部下から質問された時、あなたはどう対応すべきでしょうか?
答えは一つ。「即座に、正確に、教える」です。そして、教わる側も、分からないなら即座に聞くべきです。
道に迷った時を想像してみてください。スマートフォンの地図アプリで調べることもできますが、すぐそこに交番があって、お巡りさんに聞けば10秒で解決することなら、迷わず聞きますよね? それと同じです。
にもかかわらず、一部の企業や上司の中には、こうした「正解が決まっていること」についてすら、「それは人に聞く前に、まず自分で調べろ」「過去の資料を全部読んでから質問しろ」といった指導をするところがあります。あるいは、意図的に教えずに、相手が困るのを見ていたりします。
ハッキリ言って、これは教育でも何でもありません。ただの「時間の無駄遣い」であり、率直に言えば「愚か」か「意地悪」なだけです。
私が以前在籍していた二社目のベンチャー企業も、この罠に陥っていました。本来、口頭で5分もあれば教えられるような定型業務のやり方について、「まずは自分で考えてやってみろ」という指導をするのです。
結果、新人は何時間もかけて非効率なやり方を試行錯誤し、結局間違えてやり直しになる。その時間は、本来もっと創造的な、お客様のための営業活動や、新しい受注に繋がる戦略を考えるために使えたはずです。
部下の思考力や時間は、有限で貴重なリソースです。「正解が決まっていること」は、さっさと教え、さっさと学んでもらう。マニュアル化、FAQ化するなどして、いつでも誰でもアクセスできる状態にしておく。
そうして生まれた時間とエネルギーを、これからお話しする、より重要な「正解が決まっていない仕事」に集中させること。これが、賢明な経営者やマネジャーが最初にやるべきことなのです。
2.「正解が決まっていない仕事」→「自分で考えろ」が真価を発揮する領域
さて、ここからが本題です。育成において本当に重要で、そして難しいのが、二つ目の「正解が決まっていない仕事」です。
営業の世界は、この「正解のない問い」で満ち溢れています。
初対面のお客様に、どう挨拶すれば心を開いてもらえるか?
なかなか本音を話してくれない相手から、どうやって課題を引き出すか?
競合他社と比較された時、どう切り返せば自社の価値が伝わるか?
クロージングの場面で、どんな一言が相手の背中を押すのか?
これらに、唯一絶対の「正解」は存在しません。お客様の性格、その時の状況、自社の商品の特性、そして何より、営業担当者自身の個性によって、「最適解」は常に変化し続けます。
私が10年以上にわたる営業キャリアの中で、数千件もの飛び込み営業を経験して培ってきた、「初対面のお客様と会った瞬間の声のトーン、話すスピード、お辞儀の角度、場の雰囲気作り」といったものは、他の誰かがそのまま真似できるものではありません。
それは、数えきれないほどの成功と失敗、そして、その都度の深い思考と戦略の上に築き上げられた、私だけの「やり方(スタイル)」なのです。
こうした「正解が決まっていないもの」に対して、部下から「どうすればいいですか?」と聞かれた時。この場面でこそ、「君はどう思う?」「まずは、君のやり方でやってみれば?」という指導、すなわち「自分で考えろ」というアプローチが、真価を発揮するのです。
私も現在、コンサルタントとして営業の教育や指導を行う際には、この姿勢を非常に大切にしています。「これが100%正解だ」「このマニュアル通りにやりなさい」といった、重苦しい指導はしません。
そうではなく、「私は、こういう理由で、こうやっています。それを踏まえた上で、あなたならどうしますか?」と、問いかけるのです。
なぜなら、営業という仕事で長期的に成果を出し続け、お客様から真に信頼されるためには、誰かの真似事ではない、その人自身の経験と哲学に裏打ちされた「自分なりの勝ちパターン(やり方)」を確立することが、不可欠だからです。
そして、その「自分なりのやり方」は、他ならぬ自分自身で、試行錯誤しながら見つけ出すしかないのです。
この領域において、「自分で考えろ」と促すことは、部下を突き放しているのではなく、その人だけの唯一無二の武器を授けるための、最も誠実で効果的な指導法だと言えるでしょう。
ただし…「自分で考えろ」が“毒”になる3つの条件
さて、ここまで「正解のないものに対しては、自分で考えろ、という指導は正しい」と述べてきました。しかし、話はそう単純ではありません。
この「自分で考えろ」という言葉は、非常に強力な作用を持つ“劇薬”のようなものです。適切な相手に、適切なタイミングで、適切な環境で投与されれば、驚くほどの成長を促します。
しかし、その前提条件を一つでも間違えれば、相手の心を蝕み、可能性の芽を摘んでしまう“猛毒”へと豹変するのです。
では、その「前提条件」とは何でしょうか? 「自分で考えろ」が効果を発揮しない、むしろ有害にさえなってしまう3つのケースについて、考えていきましょう。
ケース1:相手に「考える時間」と、指導者に「待つ覚悟」がない
「自分で考える」という行為は、当然ながら時間がかかります。特に、経験の浅い新人や若手であれば、なおさらです。
一つの課題に対して、ああでもない、こうでもないと悩み、調べ、仮説を立て、実行し、失敗し、また考える…このプロセスを繰り返すには、膨大な時間とエネルギーが必要です。
指導する側は、この「時間がかかる」という事実を、まず受け入れなければなりません。
部下がすぐに答えを出せなくても、焦らず、辛抱強く見守る「忍耐力」。そして、短期的な成果(今月の売上など)を求めるのではなく、部下の長期的な成長を信じて待つ「覚悟」と「余裕」が必要です。
私が新卒で入社したベンチャー企業は、まさしくこのスタイルでした。「枠にはめず、自分で考えさせて結果を出させる」という、聞こえは良い大きな器の教育方針。
しかし、その実態は「みんな忙しすぎて、新人を指導する余裕がなかった」という側面も否めません。
結果として、私たちは自分で何とかするしかなく、半ば無理やり成長させられました。それはそれで良い経験でしたが、一歩間違えれば、多くの新人が潰れてしまっていた可能性もあります。
経営者やマネジャーが、部下の育成にかかる「時間というコスト」を許容できず、短期的な成果ばかりを求めている状態で「自分で考えろ」と言っても、それは単なるプレッシャーにしかならないのです。
ケース2:相手が「考える余裕」のない状態にある
この指導が効果を発揮しない、二つ目の非常に重要なケース。それは、言われた本人が「自分で考える」ための精神的な余裕(リソース)を持っていない場合です。
高校の部活動を想像してみてください。チームのエース級で、常にレギュラーとして活躍し、「もっと上に行くためには、どうすればいいか?」と考える余裕のある選手がいるとします。
こうした選手に、監督が「お前は、どういう選手になりたいんだ? 自分で考えて練習してみろ」と言えば、それは彼の成長を促す素晴らしい指導になるでしょう。
しかし、一方で、ようやく補欠に選ばれたばかりで、日々の厳しい練習になんとか食らいついていくので精一杯の選手がいるとします。彼は、自分のことで手一杯で、「チームのために」とか「自分の将来像」なんて考える余裕はありません。
そんな彼に、同じように「自分で考えろ」「お前はどうなりたいんだ?」と問いかけても、おそらく「え…? なんですか、それ…?」と戸惑ってしまうだけでしょう。
彼にとっては、抽象的な問いよりも、「まずは、この素振りを100回やってみろ」という、具体的で明確な指示の方が、よほどありがたいのです。
これは、ビジネスの現場でも全く同じです。営業として、あるいは社会人として、まだ通常業務を覚えるのに不慣れな段階。
組織の中で生き残ることに必死で、「自分なんかじゃ、トップセールスになんてなれない」「あの先輩みたいにはなれない」と、未来を悲観しがちになっている。
そんな精神状態の部下に、「君はどうしたいんだ? 自分で考えて契約を取ってこい」と言っても、それはただの無茶ぶりであり、心を追い詰めるだけです。
「自分で考えろ」という指導は、それを受け止め、自分事として考えるだけの「余裕」がある人にしか響かない、ということを、指導者は肝に銘じておく必要があります。
ケース3:相手が「能力を発揮できない環境」にいる
私が、指導者として最も「もったいない」と感じ、そして憤りさえ覚えるのが、この三つ目のケースです。
それは、本人は「自分で考える力」を持っているにも関わらず、劣悪な環境のせいで、その能力を全く活かせていない、という状態です。いわゆる「金の卵が、石の上で潰されている」状態と言えるでしょう。
その「悪い環境」とは、単に給与が低いとか、労働時間が長いといった物理的な条件だけを指すのではありません。
質問や提案をしても、頭ごなしに否定したり、人格攻撃をしたりするパワハラ上司の存在。
足を引っ張り合ったり、陰口を叩いたりする、協力体制のない同僚たち。
明らかに理不尽な要求を繰り返し、精神をすり減らしてくるモンスターカスタマーの存在。
社内での立場が圧倒的に不利で、正当な評価が受けられない不公平な状況。
こうした環境下に置かれた人間は、どれだけ優秀なポテンシャルを持っていたとしても、萎縮してしまい、自分の能力を著しく抑制されてしまいます。
自己肯定感は下がり、新しいことに挑戦する意欲も湧きません。そんな状態で「さあ、自分で考えろ!」と言われたところで、ポジティブな思考などできるはずがないのです。
もし、あなたの会社で「自分で考えろ」という指導がうまくいっていないとしたら、それは部下個人の能力の問題ではなく、彼らを取り巻く「環境」に、何か深刻な問題が潜んでいる可能性はないでしょうか?
経営者やマネージャーは、まず「金の卵」が安心して能力を発揮できる、安全で健全な「土壌」を整える責任があるのです。
では、どうすればいいのか? 真の「自分で考えろ」への道筋
では、まだ「自分で考えろ」という“劇薬”が効かない、未熟な段階にいる部下に対して、私たちはどのように接すれば良いのでしょうか?
突き放すのではなく、かといって過保護に教えすぎるのでもなく、その答えは、2つのアプローチに集約されます。
① まずは、その人の「レベル」を引き上げることに注力する
「自分で考えろ」と言える段階に達していないのであれば、話はシンプルです。指導者の役割は、まずその段階まで、本人のレベルを引き上げてあげることです。あるいは、本人が自力でそこに到達するまで、じっと待つことも必要です。
具体的な業務のやり方(正解があるもの)を丁寧に教え、小さな成功体験を一つひとつ積ませることで、「やればできる」という自己効力感を育んであげる。焦らず、一歩ずつ、階段を上る手助けをすることです。
② 「希望」を説き、可能性の扉を開けておく
日々の業務に追われ、自信を失っている若手は、「自分には無理だ」と、自ら未来への扉を閉ざしてしまいがちです。そんな彼らに対して、指導者は「希望」を説く必要があります。
「今は大変かもしれないけれど、君のこういうところは素晴らしいと思う。だから、何かのきっかけさえ掴めば、君もいつか必ず、自分で考えて道を切り拓ける領域に行けるはずだ」
これは、単なる綺麗事や気休めではありません。人間は、いつ、どんなきっかけで才能が花開くか、誰にも分からないのです。その「可能性」を信じ、伝え続けること。それが、部下の心の火を消さないために、指導者ができる非常に重要な役割なのです。
もちろんこの希望の言葉の前提として、①でお話ししたように、相手のレベルを引き上げる具体的な対策が必要です。しかし、あくまでメンバーに希望を捨てさせないために、ポジティブな言葉をかける必要があります。
あなたの「次の一歩」:言葉を一つ、変えてみる
「自分で考えろ」という指導は、突き詰めれば正しい。なぜなら、特に「正解のない」営業の世界では、最終的には自分自身の頭で考え、決断し、行動するしかないからです。
しかし、その言葉が本当に部下の力になるためには、それを受け止めるだけの「レベル」と「余裕」、そして「環境」が整っている必要があります。
そして、部下が今どの段階にいるのかを冷静に見極め、その状態に合わせて指導法を柔軟に変えていくことこそ、指導者に求められる最も重要な役割なのです。
さて、この長いコラムをここまで読んでくださった、熱心な経営者、そして営業マネジャーのあなたへ。最後に、明日からすぐに実践できる「次の一歩」を提案させてください。
次に、部下への指導の場面で「自分で考えろ」という言葉が口から出そうになったら、ぐっと一度こらえて、代わりにこう問いかけてみてください。
「なるほど。まずは、君がどう思うか、考えを聞かせてほしい」
「自分で考えろ」と突き放すのではなく、「君の考えを聞かせてほしい」と一緒に考える“対話の入口”を作る。
たったこれだけの小さな言葉の変化が、部下の思考を止めず、信頼関係を育み、自律的な成長を促す、大きな一歩になるはずです。
その「呪いの言葉」、解き放ちませんか?
あなたの会社では、「自分で考えろ」という言葉が、部下の成長を止める“呪いの言葉”になってしまってはいませんか?
一人ひとりの社員が持つ無限の可能性を最大限に引き出し、やらされ仕事ではなく、自らの意志で考え、行動し、お客様から感謝されながら契約を獲得してくる。
そんな、自律的で強い営業組織を本気で作りたいとお考えの経営者の方は、ぜひ一度、トレテクにご相談ください。
トレテクは、単一的な指導法を押し付けるのではなく、貴社の文化と、メンバー一人ひとりの状況に合わせた、最適な人材育成の仕組み作りを、共に考え、サポートします。
部下を信じ、待ち、そして導く。真の意味での「自分で考えさせる」育成法を、あなたの会社に根付かせてみませんか。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの会社の「人」に関するお悩みをお聞かせください。
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。よろしければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。
あなたの、そして貴社の営業メンバーが、「自分で考え、動く」ことのできる自律的な人材に成長することを楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。