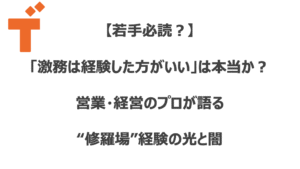「自分で考えろ」という指導の仕方について
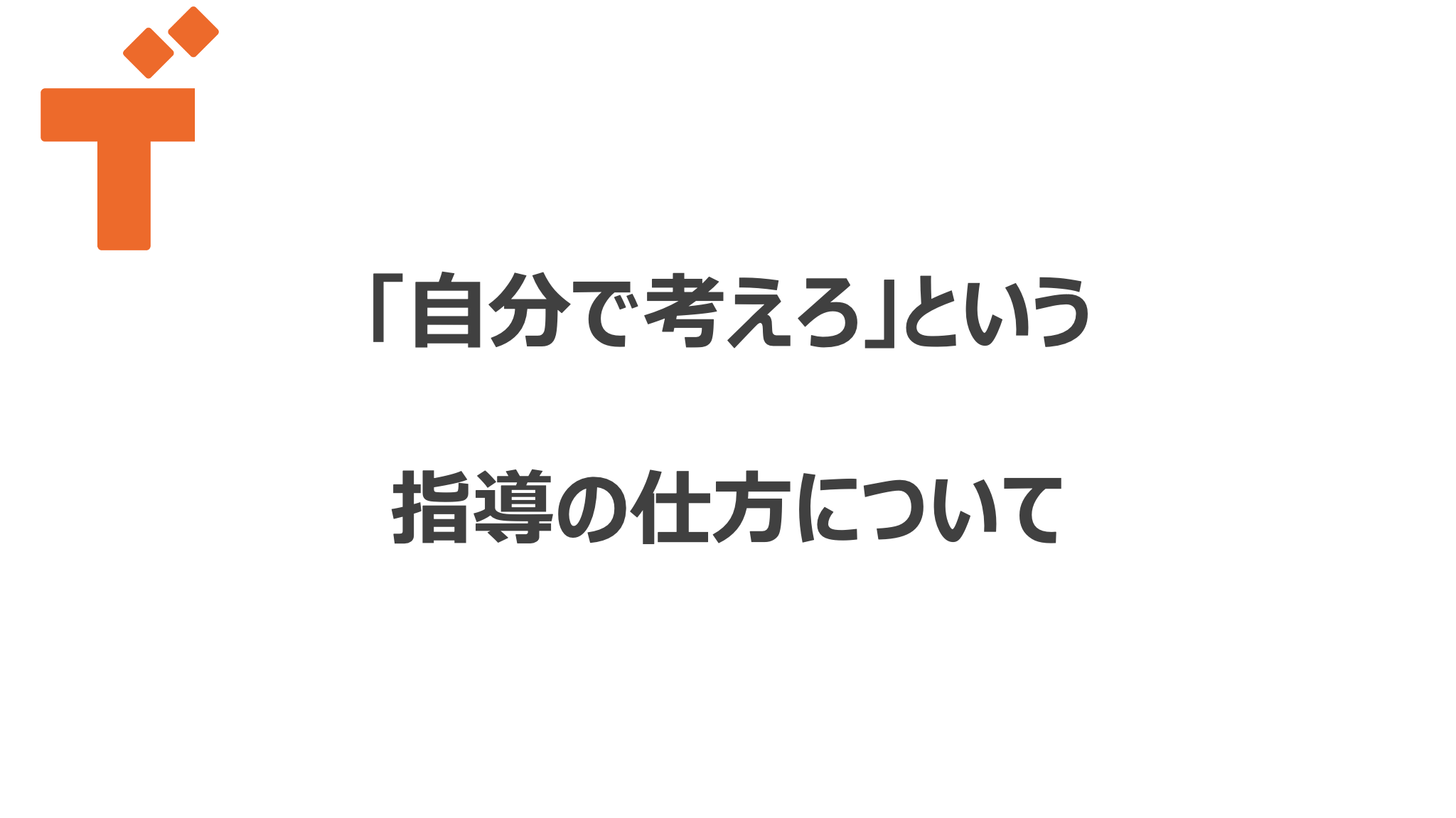
上司や先輩が言い放つ「自分で考えろ」
「自分で考えろ」という指導について考えることが多くあります。
この言葉、上司や先輩から言われた経験がある方も多いのではないでしょうか?
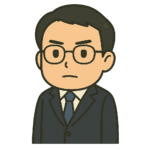 トレテク 久保埜
トレテク 久保埜私が二つのベンチャー企業で営業をしていた時も、
この言葉を何回も言われました。
「自分で考えろ」という指導をするにあたり、ふさわしい場面とそうでない場面があります。
いったいどう使えば効果的な指導になるのでしょうか。
貴社の営業力を飛躍させる「実践型」コンサルタント
ベンチャー・大企業合わせて約20年の現場経験を持つ私が、貴社に再現性のある「売れる仕組み」を構築します。
現場の泥臭さを経験しているからこその営業視点を強みとして、座学研修のほか、今日からすぐに使える実践的なノウハウで、特に商談・プレゼン力の向上に貢献します。
「売上を伸ばしたいが、何から手をつければ…」とお悩みの経営者・営業部長様へ、実践型コンサルティングで、貴社の営業チームを強化し、確かな成果へと導きます。


「自分で考えろ」と言われても…
上司や先輩から「自分で考えろ」と言われた時、ある程度営業経験がある方であれば、
「ここから先は自分の裁量なんだな」と考えることができます。
しかし新人や経験の浅い方にとっては、
- 「いやいや、ちゃんと教えてくださいよ…」
- 「それって指導でも何でもないだろう」
- 「指導せず放置??」
と思う方も多いと思います。
しかしこの指導は、新人営業や経験の浅い人にとっては成長のチャンスにつながる場合があります。
そういった意味で非常に重要なポイントです。
仕事には2種類ある:正解が決まっているものと決まっていないもの
まず前提をお話しします。仕事や学びには大きく分けて2種類あります。
1. 正解が決まっているもの
例えば、パソコン操作などがこれにあたります。
「このボタンを押せば印刷できる」というような、明確に答えが決まっているものです。
正解が一つしかなく、人によって違う答えはないものです。
2. 正解が決まっていないもの
一方で、営業の世界では「初対面の人にどう挨拶したら心を開いてもらえるか」というような、正解が決まっていない問いが多く存在します。
私は10年以上複数の業界で営業をしてきて、数千件もの飛び込み営業を経験してきました。その中で培った「感覚」があります。
初対面でお客様と会った時の声のトーン、話し方、聞き方、お辞儀の角度、雰囲気作りなど、これらは私自身が経験と思考と戦略の上に築き上げた「私のやり方」なのです。
このような「正解が決まっていないもの」は、営業の世界では非常に多いです。
丁寧なマニュアル通りの説明が効果的なお客様もいれば、「そういうのは面倒くさい」「嘘くさい」と感じるお客様もいます。
営業職や社会人として成長していく中で、私たちはこうした「正解が決まっていないもの」に常に直面しています。
「自分で考えろ」の指導で正しいもの
「正解が決まっていないもの」に対しては、上司や先輩から「自分で考えろ」「お前はどう思うの?」「じゃあそれでやってみれば?」という指導を受けることが多いと思います。
まず、私はこれについては【正しい】と思っています。
私は現在営業の教育指導をしたり、相談を持ちかけられたりする立場にいます。そこでも「自分で考えろ」という姿勢を大切にしています。
「私はこうやっています。なぜならこう思っているからです。皆さんはどう思いますか?」
というアプローチを取っています。
「これが100%正解だ」「この通りにやれ」という重苦しい指導はしていません。ただ一つ正解を探すのではなく、その人なりの「やり方」を身につけることが重要です。
正解が決まっているものへの対応
一方、「正解が決まっているもの」に関しては、教える側は即座に教えるべきだと思います。そして、教わる側も即座に聞くべきです。
例えば、道に迷った時に、Google検索で調べることもできますが、通行人に聞いた方が早い場合があります。そういう時は迷わず聞けばいいのです。
正解が決まっているものについて、「それは人に聞くんじゃなくて自分で調べて勉強してください」という教え方や、あえて教えないという文化の企業がありますが、率直に言って愚かだと思います。あるいは意地悪なだけです。
正解が決まっている分野では、サクッと教えて、サクッと学ぶ。
そして、その分野には時間と労力をあまりかけず、もっと重要なことに集中するべきです。
私が在籍していた二社目のベンチャー企業も、提携業務を自分で考えさせる指導でした。
口頭で教えてくれればできるものを、時間をかけて考えさせたりと、今思えば非効率な指導だと感じています。自分で考えることの対象が、まさに「正解が決まっているもの」でした。
「自分で考えろ」指導の問題
あなたがベテラン営業もしくはマネジャーの場合、1年目の新人から、「これはどうすればいいですか?」「これでいいですか?」とたくさん質問してくることでしょう。
前述の通り、正解のないものについては「自分で考えろ」「お前どう思ってるの?」「そう思うならそれでやってみれば?」という答え方は『ある程度』正解だと思います。
ただし、『ある程度』と書いた通り、「自分で考えろ」という指導にはいくつかの問題があります。
1. 時間がかかる
自分で考えさせるという指導法は、指導される側に特に時間がかかるため、新人が成長するまでは辛抱強く長い目で見る必要があります。
新人が「自分で考える」ようになるまでに、上司は余裕や忍耐強さが必要です。また新人自身も、「営業含めビジネスには正解がないことも多々ある」という現実を認める誠実さが必要です。
私が新卒で入社したベンチャー企業では、さまざまなアイデアを用い結果を出させるため、あえて指導をしないという文化がありました。
枠で押さえつけるのではなく、「自分で考えろ」という、大きな器の教育をしているのです(みんな忙しすぎて指導する余裕がなかったというのもありますが)。
時間がかかっても、”自分でなんとかする”ことで、半ば無理やり成長させられました。当時は大変でしたが、今振り返ると良い経験でした。
2. 人の状態によっては効果がない
「自分で考えろ」という指導は、言われた人の状態によっては効果がない時があります。
例えば、高校の部活で補欠の選手を考えてみましょう。力がなくて、レギュラー選手のように一定の成果が残せず、一生懸命に練習に食らいついている選手がいるとします。
こうした選手に「自分で考えろ」「お前はどうなりたいの?」と聞いても、ピンと来ないでしょう。「え、何それ?」となってしまいます。日々の練習で精一杯の段階では、そういう大きな視点での指導は響かないのです。
この指導が効果的なのは、ある程度レギュラー格で、上を見る余裕がある選手です。「自分はどうしたいか」を考える余裕がある人にしか響かないのです。
3.環境によって能力が発揮できない場合がある
私がもったい無いと思うのは、「自分で考える頭はあるのに、悪い環境のもとでそれを活かせていない人」の存在です。いわゆる「金の卵が潰されている」状態です。
その悪い環境とは例えば、労働条件の劣悪さだけでなく、パワハラ上司、意地悪な同僚、圧倒的不利な社内での立場、モンスターカスタマーによって、著しく自分の能力を抑制されている時です。
未熟な段階の人への指導
では、まだ「自分で考えろ」という指導が響かない段階の人には、どう接すればいいのでしょうか?
①その人のレベルを引き上げる
「自分で考えろ」という段階に行くためには、まずその人のレベルを引き上げる必要があります。もしくはそこに到達するまで待つことも必要です。
②希望を説く
通常業務に不慣れな段階では、組織の中で生き残ることに精一杯で、「俺なんかできない」「あんなふうになれない」と未来を閉ざしてしまいがちです。
しかし、人間はいつ花開くかわかりません。「何かのきっかけで君もその領域に行く可能性はある」ということを、綺麗事ではない範囲で伝えることが大切です。
まとめ:「自分で考えろ」という指導の本質
「自分で考えろ」という指導は基本的に正しいと思います。特に「正解が決まっていないもの」に対しては、最終的には自分で考えるしかないからです。
しかし、この指導が効果を発揮するためには、それが耳に入ってくるレベルと余裕と環境が整っていることが必要です。それに達しているかどうかを見極めることも、指導者の重要な役割です。
営業として、営業マネジャーとして、あるいは経営者として人を育てる立場にある方は、「正解が決まっているもの」と「正解が決まっていないもの」を区別し、適切な指導法を選ぶことが大切です。
そして何より、目の前の人がどの段階にいるかを見極め、その人に合わせることが真の「自分で考えろ」という指導なのではないでしょうか。
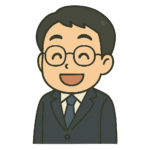
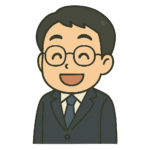
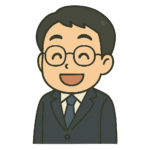
営業の世界でも、他のどんな分野でも、最終的に人を大きく成長させるのは「自分で考える力」です。
その力を育てるために、私たちはどのような指導をすべきか、今一度考えてみる価値があると思います。