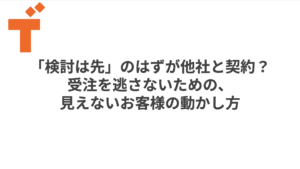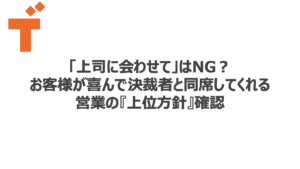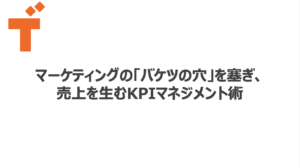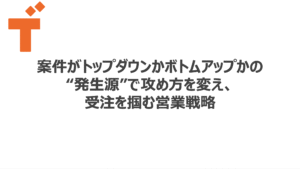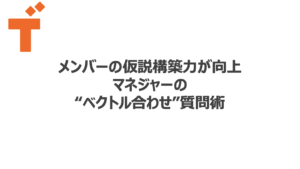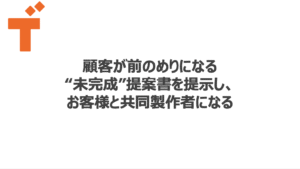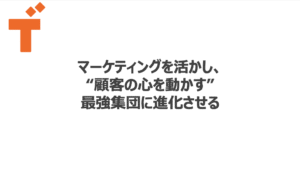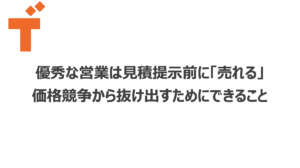【SPIN話法後編】SPIN話法を日本式にアレンジし、営業で使いこなす
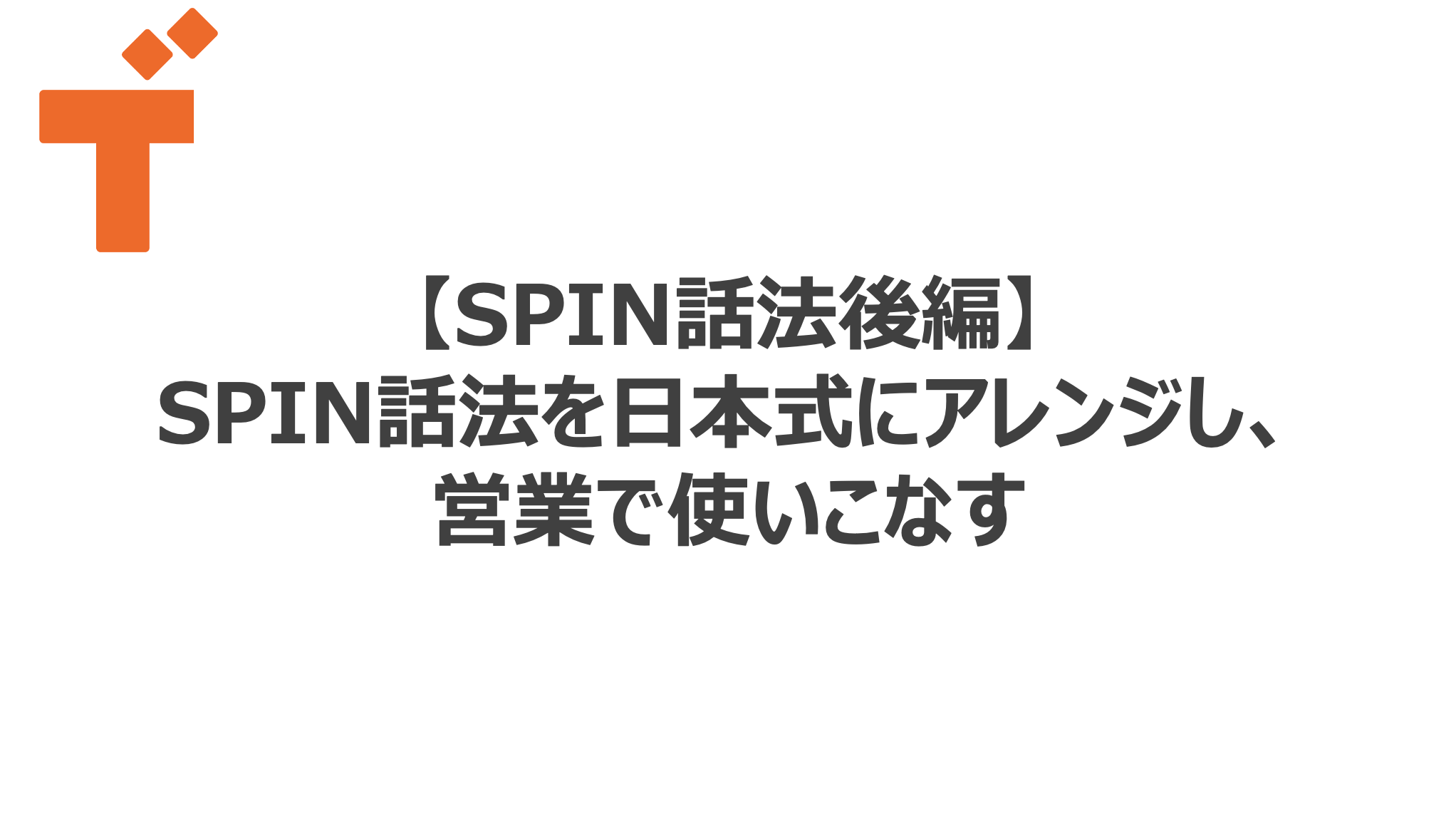
【SPIN話法前編】のコラムでは、世界中のトップセールスが実践する営業話法、「SPIN」の基本的な考え方とその構造(4つの質問)について解説しました。
「なるほど、これは強力な武器になりそうだ!」と感じていただけた方も多いのではないでしょうか。
しかし、同時にこんな声も聞こえてきそうです。
「理論は分かった。でも、実際に商談の現場でどう使えばいいんだ?」
「特に、あの『示唆質問(I)』って、相手の痛いところを突くようで、なんだか難しそう…」
「そもそも、これって欧米のテクニックでしょ? 日本のビジネス文化の中で使ったら、かえってギクシャクしないかな?」
そう、素晴らしい理論やフレームワークも、実践できなければ意味がありません。特にSPIN話法は、そのパワフルさゆえに、「難解だ」「使いこなせない」と感じてしまう営業担当者や経営者の方がいらっしゃるのも事実です。
ですが、どうぞご安心ください。後編では、そんなあなたの疑問や不安に真正面からお答えします。
SPIN話法を明日からの営業現場で確実に活かすための具体的な実践テクニック、そして、日本のビジネス環境でもスムーズに、かつ効果的に成果を出すための「日本式アレンジ」の極意を、余すところなく伝授いたします。
前編でSPINの可能性に気づいたあなたへ。この後編を読めば、その武器を自在に使いこなし、受注を量産し、売上を飛躍的に伸ばすための、具体的な道筋が見えてくるはずです。
貴社の営業力を飛躍させる「実践型」コンサルタント
ベンチャー・大企業合わせて約20年以上営業現場経験を武器に、貴社に再現性のある「売れる仕組み」を構築します。
現在も営業職として現場の泥臭さを経験しているからこその営業視点を強みとして、座学研修のほか、今日からすぐに使える実践的なノウハウで、特に商談・プレゼン力の向上に貢献します。
「売上を伸ばしたいが、何から手をつければ…」とお悩みの経営者・営業部長様へ、実践型コンサルティングで、貴社の営業チームを強化し、確かな成果へと導きます。

その心理的なハードル、痛いほど分かります ~ SPIN実践の壁
SPIN話法について学ぶと、多くの方がその論理性と効果に感銘を受けます。「これだ!」と。しかし、いざ実践しようとすると、途端に壁にぶつかるケースが少なくありません。
特に、お客様の問題がもたらすマイナスの影響を深掘りする「示唆質問(Implication Questions)」は、多くの日本人営業にとって心理的なハードルが高いようです。
「こんな踏み込んだ質問をして、相手を怒らせたらどうしよう…」「場の空気が悪くなったら、その後の提案どころじゃなくなる…」そんな不安から、どうしても当たり障りのない質問に終始してしまい、SPINの持つ本来の力を引き出せずに終わってしまう。
また、「そもそも外資系の理論でしょ?」「ロジカルすぎる話し方は、日本のウェットな人間関係の中では敬遠されるんじゃないか?」といった、文化的なギャップに対する懸念の声もよく耳にします。
確かに、相手への配慮や和を重んじる日本のビジネス文化において、欧米流のストレートな質問が常に最適とは限りません。
こうした「難しさ」や「不安」を感じるのは、あなただけではありません。私も、そして私が指導してきた多くの営業も、同じような壁にぶつかってきました。
しかし、断言します。SPIN話法は、日本のビジネス環境においても間違いなく有効です。そして、いくつかの「コツ」と「日本式のアレンジ」を加えることで、誰でも驚くほどスムーズに、そして効果的に使いこなせるようになるのです。
大前提その① あなたの「きく」はどのレベル? ~ ヒアリングの3つの段階
SPIN話法の具体的なテクニックに入る前に、まず大前提として、皆さんの「きく」という行為そのものについて、少しだけ意識を向けてみましょう。実は、「きく」には3つの異なるレベルがあるのです。英語で考えると分かりやすいかもしれません。
リスニング (Listening / 聞く)
これは、単に音が耳に入ってきて、鼓膜が震えているだけの状態です。相手の話の内容を理解しようという意図はあまりなく、BGMのように聞き流している状態に近いかもしれません。
アスキング (Asking / 訊く)
これは、自分が知りたい情報や、聞きたいと思っていることだけを、質問によって相手から引き出そうとする状態です。
例えば、事前に用意した質問リスト(スクリプト)に沿って、順番に質問していくのは、典型的なアスキングと言えるでしょう。自分の目的達成が主眼であり、相手の状況や心情への配慮は二の次になりがちです。
残念ながら、多くの営業の「ヒアリング」は、このアスキングのレベルに留まってしまっていることが多いのです。
ヒアリング (Hearing / 聴く)
これこそが、私たちが目指すべき「きく」のレベルです。相手の話に真剣に耳を傾け、言葉の表面的な意味だけでなく、その裏にある感情や意図、本当に伝えたいこと(=心の声)までをも深く理解しようと努める状態です。
相手の立場に立ち、共感しながら、相手自身も気づいていないような本音や課題を引き出していく。これが真のヒアリングです。
SPIN話法は、単なる質問リストではありません。それは、この「ヒアリング(聴く)」のレベルを実現するための、思考のフレームワークであり、コミュニケーションの技術なのです。
まず、「自分は今、どのレベルで相手の話をきいているだろうか?」と自問自答し、「アスキング」から「ヒアリング」へと意識をシフトさせることが、SPINを使いこなすための第一歩となります。
大前提その② なぜお客様は買ってくれない? 心の壁「4つの不」を理解する
次に、SPIN話法を実践的な武器にするために理解しておきたいのが、お客様が購買に至らない心理的な障壁、通称「4つの不」です。これは、お客様がお断りをする際の、代表的な理由のパターンとも言えます。
不信 (Distrust)
「この営業担当者、本当に信頼できるのかな?」「この会社、大丈夫なのかな?」という、相手(人・会社)に対する不信感。
不要 (No Need)
「そもそも、この商品やサービス、自分には必要ないんだけど…」という、ニーズそのものの欠如。
不適 (Not Suitable)
「商品は良さそうだけど、ウチの状況には合わないんじゃないかな…」「もっと自社に適した他の選択肢がありそうだ」という、適合性への疑問。
不急 (No Hurry)
「必要性も感じるし、商品も悪くない。でも、今すぐじゃなくてもいいかな…」という、緊急性の欠如。
お客様は、この4つの「不」の壁をすべてクリアしない限り、購買という行動には至りません。そして、SPIN話法は、まさにこの「不信」→「不要」→「不適」→「不急」という順番で、お客様の心理的な壁を一つひとつ、丁寧に取り除いていくプロセスでもあるのです。
商談が思うように進まない時、「今、お客様はどの『不』の壁にぶつかっているのだろうか?」と考えてみてください。その壁が見えれば、打つべき手も自ずと明らかになってきます。
最初の関門「不信」を突破せよ! ラポールとWhy you now
営業活動において、まず最初に突破しなければならないのが、「不信」の壁です。どんなに素晴らしい提案も、相手に「この人は信頼できない」と思われてしまっては、聞く耳を持ってもらえません。
この「不信」を解消し、安心して話を聞いてもらえる土台を作るために、特に有効なのが「ラポール形成」と「Why you now」の提示です。
1.ラポール(心の橋)を架ける技術 ~ 「関係性」が鍵!
ラポールとは、フランス語で「橋をかける」という意味。心理学の用語で、相手との間に築かれる、安心感や親近感、信頼関係のことを指します。
ラポールを築く基本は、「相手を褒める」「相手に共感する」ことですが、これを意識的に実践できている営業は、意外と少ないものです。
特に電話営業などでは、いきなり「本日は〇〇の件で…」と用件から入ってしまいがち。しかし、対面での訪問営業なら、名刺交換の後、「今日は良いお天気ですね」「素敵なオフィスですね」といった雑談から入りますよね? 電話でも、訪問でも、まずはお客様との間に心の橋を架ける意識が重要です。
ただし、「褒める」「共感する」を意識しすぎると、かえって相手に「媚びている」「お世辞っぽい」という印象を与え、逆効果になることも。そこで、私が特にお勧めしたいのが「関係性を利用したラポール形成」です。
例えば、共通の知人がいる場合。
「実は、御社の〇〇専務と、弊社の上司の△△が大学の同期だそうでして、△△からくれぐれもよろしくお伝えください、と申しつかっております」
といった一言があるだけで、場の空気は和らぎ、相手はあなたに対して少し親近感を覚えてくれます。
もし直接的な関係性が見つからない場合は、お客様の会社やサービス、取り組みなどについて、具体的に触れて共感や称賛を示すのが有効です。
例えば、
「御社のゲームアプリ、うちの子供が大好きで毎日夢中で遊んでいるんです。今日は子供に代わって、まず御礼をお伝えさせてください。いつも楽しい時間をありがとうございます!」
といった言葉。
こうした働きかけによって、お客様から「はい」や「ありがとうございます」といった肯定的な返事を引き出すことができれば、しめたもの。
これは心理学で「フットインザドア効果」と呼ばれるもので、最初の小さな要求(この場合は肯定的な返事)を受け入れてもらうと、その後の要求(本題の話を聞いてもらうなど)も受け入れられやすくなる、という効果が期待できます。
まずは、相手に心を開いてもらうための、小さな「YES」を積み重ねていきましょう。
2.「Why you now」で心を掴む! ~ なぜ今、あなたに話すのか?
ラポールを築き、お客様が少し心を開いてくれたら、次に提示すべきなのが「Why you now」、つまり「なぜ“今”、私が“あなた(御社)”にご連絡(ご提案)しているのか」という、明確な理由です。
ただ漠然と「良い商品なのでご紹介に…」では、お客様の心は動きません。「なぜ、他の誰でもなく、このタイミングで、自分に話を持ち掛けてきたのか?」その必然性、いわば「今、聞くべき理由」をしっかりと示すことで、お客様はあなたの話にグッと引き込まれるのです。
この「Why you now」を効果的に伝えるためには、以下の4つの観点に触れると良いでしょう。
- お客様(御社)の状況:例「御社のビジネスが現在、急速に拡大されており…」
- 市場の状況:例「〇〇市場全体が大きな変革期を迎えており…」
- 競合の状況:例「競合のB社が最近、〇〇という動きを見せており…」
- お客様のお客様(エンドユーザー)の状況:例「御社のお客様である〇〇層のニーズが、このように変化してきており…」
多くの場合、営業はこのうち1つか2つの観点にしか触れません。
しかし、これら4つの観点を複合的に示し、「だからこそ“今”、御社にとってこの話を聞くことが非常に重要(あるいはチャンス)なのです」とストーリーを組み立てることで、「今感」は飛躍的に高まり、お客様は「なるほど、確かに今、この話を聞いておくべきかもしれない」と感じてくれるはずです。
いよいよ実践!SPINを日本式に使いこなす“アレンジ術”
さあ、ラポールとWhy you nowで「不信」の壁を突破したら、いよいよSPIN話法の本番です。前編で学んだS→P→I→Nの4つの質問を、日本のビジネス文化に合わせて、よりスムーズに、そして効果的に実践するための“アレンジ術”をご紹介しましょう。
S:状況質問 → 「仮説提示型クローズドクエスチョン」で効率化!
- 日本式アレンジ:オープンクエスチョン(例:「最近の状況はいかがですか?」)は、お客様に考える負担を与え、答えにくい場合が多いです。
そこで、事前に立てた仮説を提示し、「〇〇という状況と推察しますが、合っていますでしょうか?」と、YES/NOで簡単に答えられるクローズドクエスチョンで聞くのがお勧めです。
これにより、お客様の負担を減らしつつ、効率的に現状認識をすり合わせることができます。
P:問題質問 → 「第三者話法(マイフレンドジョン)」で角を立てずに!
- 日本式アレンジ:「〇〇について、何か問題はありませんか?」と直接的に聞くのは、相手によっては失礼に感じられたり、警戒されたりする可能性があります。
そこで有効なのが「第三者話法」です。
「実は、同業の他社様で、最近〇〇といった課題(問題)をよくお伺いするのですが、御社では同様のことはございませんか?」といった形で、第三者の事例を挙げることで、お客様は「ああ、ウチだけじゃないんだな」と安心し、本音の問題点を話しやすくなります。
I:示唆質問 → 「ポジティブ転換」&「定量化」で未来を描く!
- 日本式アレンジ:SPINの最難関である示唆質問。「この問題を放置すると、どんなマイナスの影響がありますか?」と聞くのが基本ですが、これが言いづらい場合は、発想を転換し、ポジティブな側面から質問してみましょう。
「もし、この〇〇という問題(課題)が解決できたとしたら、御社にとっては、どれくらいプラスのメリットがあるとお考えになりますか?」と。
さらに、定量的な効果を尋ねるのも有効です。
「仮に、御社の受注率が10%改善した場合、年間の売上には、およそどれくらいのインパクトがあると思われますか?
このように聞かれると、お客様は頭の中で具体的な数字を計算し始め、「なるほど、解決すればこんなに大きな価値があるのか!」と、問題解決の重要性をより強く認識するようになります。
ネガティブな影響を想起させるのではなく、ポジティブな未来を想像させることで、前向きな課題認識を促すのです。
N:解決質問 → 「成功事例」で具体化し、「不急」の壁を壊す!
- 日本式アレンジ:解決質問では、お客様に解決後の理想像を語ってもらうのが基本ですが、それだけでは「そうは言っても、本当に実現できるの?」という不安が残る場合があります。
そこで効果的なのが、具体的な「成功事例」の提示です。
「実は、先ほどお話しいただいたようなプラスの効果を、実際に実現されたお客様がいらっしゃいまして…。例えば、△△社様では…」と、実例を交えて語ることで、お客様は「なるほど、自分たちもこうなれるかもしれない!」と、課題解決のイメージをより具体的に、そして現実的に捉えることができます。
これにより、「必要だけど、急いでない(不急)」という最後の壁を壊し、「これは急いで取り組むべきだ!」という気持ちへと変化させることができるのです。 - 事例選びのコツ:必ずしもお客様と全く同じ業界・規模の事例である必要はありません。
用意すべきは「業界一致事例」(同じ業界での成功例)と「課題一致事例」(業界は違うが、類似の課題を解決した例)の2種類。
「違う業界なのですが、御社が今まさに抱えていらっしゃる〇〇という課題と、非常によく似た課題を解決された事例がありまして…」と切り出せば、お客様は十分に自分事として捉えてくれます。
このように、SPIN話法の基本的な流れは守りつつ、質問の仕方や表現に少し「日本式のアレンジ」を加えるだけで、驚くほどスムーズに、そして効果的に実践できるようになります。
あなたの「次の一歩」:まずは「最初の数秒」を変えてみる
SPIN話法実践への道筋、そしてその効果、具体的にイメージできたでしょうか?
理論を学び、事例を知ることも大切ですが、何より重要なのは、やはり「やってみること」です。難しく考えすぎず、まずは小さな一歩から始めてみませんか?
あなたの「次の一歩」はこれです。
次回の営業アポイントを取る電話、あるいは訪問先での最初の挨拶の場面で、いきなり本題に入る前に、何か一つで良いので「ラポール形成」を意識した一言を加えてみてください。
相手の会社のウェブサイトを見て気づいたことへの共感(例:「〇〇の取り組み、素晴らしいですね!」)、共通の知人の話題、あるいはシンプルに天候やオフィスに関するポジティブな一言でも構いません。
そして、もし可能であれば、「なぜ“今”、御社にご連絡(お伺い)したのか(=Why you now)」を、簡潔に、しかし熱意を込めて伝えてみてください。
たったこれだけ、商談の「最初の数秒」のコミュニケーションを変えるだけでも、その後の空気感や、お客様のあなたに対する印象は、きっと変わってくるはずです。まずは、この小さな成功体験を積み重ねていくことが、SPINを体得する近道です。
SPINを「知っている」から「使いこなせる」へ
SPIN話法。それは、単なる営業テクニックではありません。お客様の心に深く寄り添い、真の課題を発見し、共に未来を創造していくための、コミュニケーション哲学そのものと言えるかもしれません。
その理論を知っているだけでは、宝の持ち腐れです。実践し、習熟し、チーム全体で共有し、定着させてこそ、SPINはその真価を発揮し、あなたの会社の営業を、そして売上を、次のステージへと押し上げてくれます。
- SPIN話法を、単なる知識ではなく、チーム全員が使いこなせる「実践スキル」にしたい。
- 日本のビジネス文化に合わせた、自社独自の「SPIN活用術」を確立したい。
- 営業チーム全体のコミュニケーション能力を底上げし、持続的な売上成長の基盤を築きたい。
もし、あなたが経営者として、あるいは営業リーダーとして、そう強く願うのであれば、ぜひ一度ご相談ください。
トレテクは、SPIN話法の理論研修はもちろんのこと、貴社の状況や商材に合わせた実践的なカスタマイズ、現場で即使えるロールプレイング、そしてスキルを確実に定着させるためのフォローアップ体制まで、一貫したサポートを提供します。
まずは、60分間の無料オンライン相談で、貴社の現状の課題や、目指したい未来について、気軽にお話しいただければと思います。無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。下記のリンクから、今すぐ無料相談にお申し込みいただけます。
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。よろしければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。
あなたの、そして貴社の営業が、お客様から心から信頼され、選ばれ続ける存在になるためのお手伝いができることを、楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。