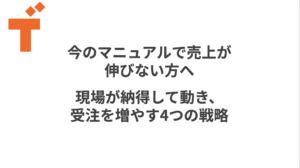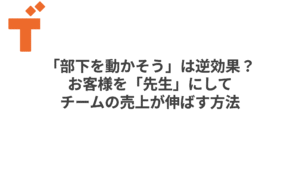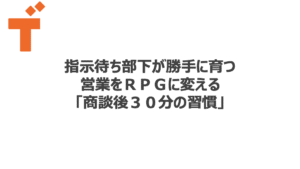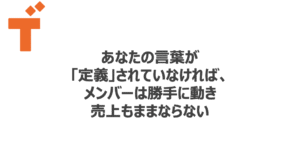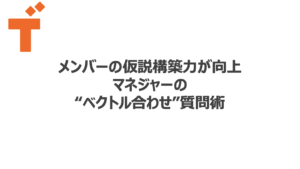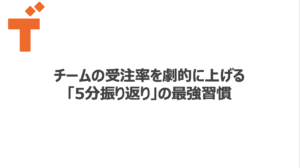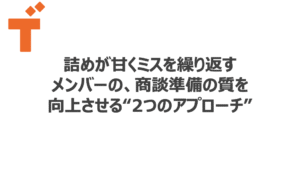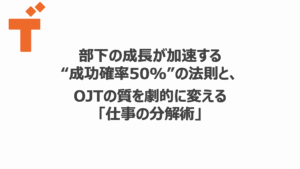「部下を信じたい気持ち」と「成果への焦り」の板挟み マネジャーに勧める「逆説のマネジメント」
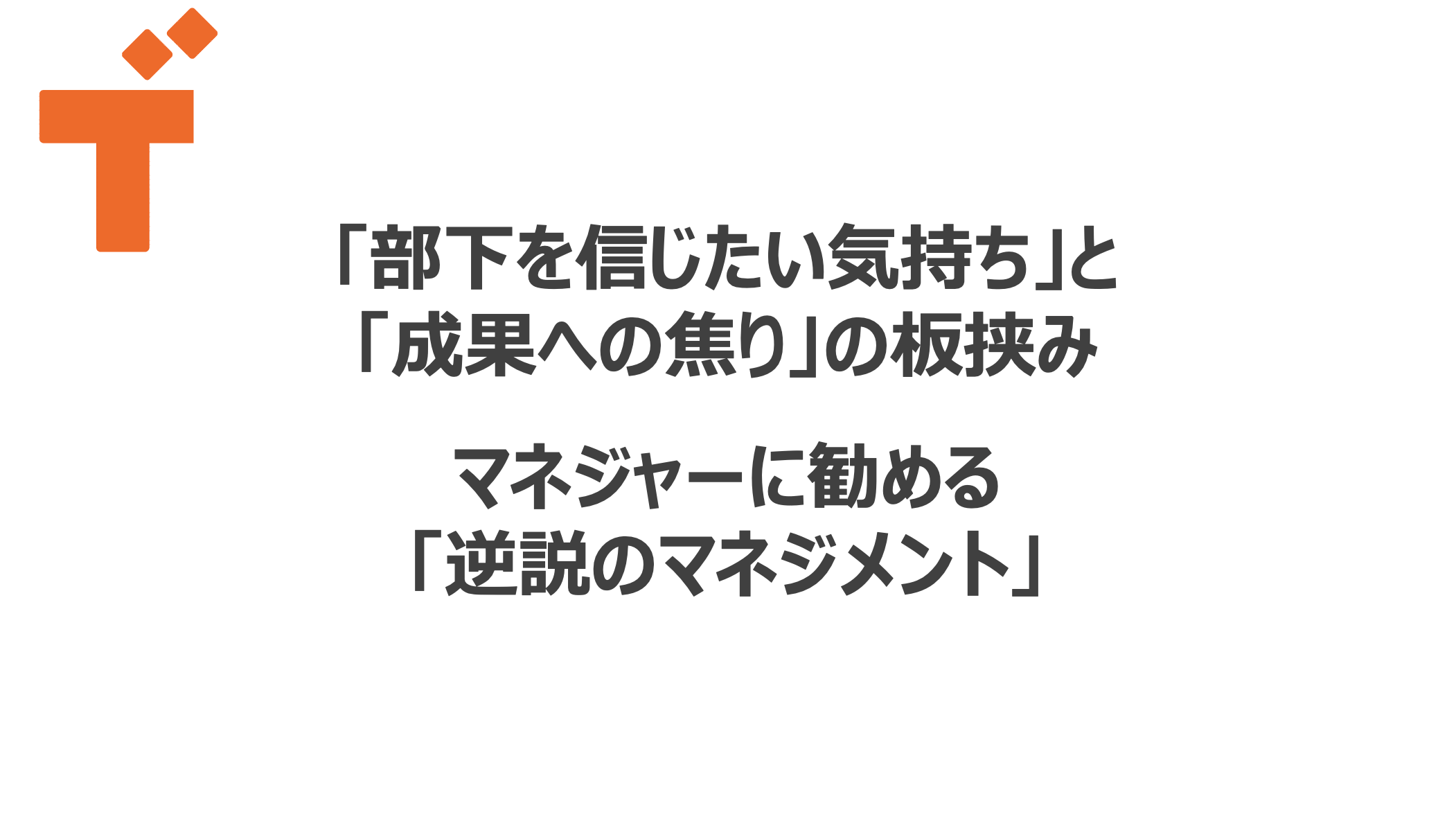
マネジャー「今日の商談のゴールは何だっけ?」
メンバー「はい、A商品の基本合意をいただくことです!」
マネジャー「そうか、わかった。じゃあ、頑張ろう」
営業所の朝、当たり前のように交わされるこの会話。しかし、あなたの心の奥底では、こんな声が渦巻いていませんか?
「…本当に大丈夫か? 彼の準備は万全なのだろうか。あの顧客のキーマンは気難しいぞ。何かヘマをしないだろうか…」
部下を思うあまり、その一挙手一投足が気になって仕方がない。しかし、細かく口出しすれば「信頼されていない」とヘソを曲げるかもしれない。結局、不安を胸にしまい込み、「頑張れ」と送り出すしかない…。
この記事は、そんな「部下を信じたい気持ち」と「成果への焦り」の板挟みになり、正しい指導法を見失ってしまっている、誠実で、真面目なすべての経営者、そして営業マネジャーのために書きました。
この記事を読めば、なぜあなたの善意に満ちた指導が空回りし、メンバーの成長をかえって妨げているのか、その衝撃的な根本原因がわかります。そして、あなたのマネジメントを180度転換させ、メンバーの潜在能力を最大限に引き出すための、「楽観」と「悲観」の正しい使い方を習得できるはずです。
「こと(事柄)に楽観、ひと(人)に悲観」が、チームを蝕む
残念なお知らせがあります。もしあなたが、部下のことを心配し、案件の成功を祈る、ごく普通の良きマネジャーであるなら、あなたの「楽観」と「悲観」の使い方は、おそらく完全に間違っています。
多くのマネジャーは、無意識のうちに、次のような思考パターンに陥っています。
- 「こと(商談・案件)」に対しては、楽観的。
「まあ、あの案件は大丈夫だろう」
「お客様も乗り気だったし、きっとうまくいくはずだ」
「競合も大したことない。今回は受注できるだろう」 - 「ひと(メンバー・部下)」に対しては、悲観的。
「彼に任せて、本当に大丈夫だろうか…」
「彼女はまだ経験が浅いから、失敗するんじゃないか…」
「なんで、あいつは言われたことすらできないんだ…」
心当たりはありませんか? 案件そのものに対しては「きっとうまくいく」と希望的観測を抱き、それを実行するメンバー個人に対しては「本当に大丈夫か?」と不安や不信の目を向けてしまう。
そして、万が一商談がうまくいかなかったとき、その矛先はどこに向かうでしょうか。 「ほら、やっぱりダメだったじゃないか!」「だから君はダメなんだ!」と、メンバー個人を責め立てる。根拠のない楽観が裏切られた反動で、メンバーへの悲観がさらに強固なものになっていくのです。
この「こと(事柄)に楽観、ひと(人)に悲観」というマネジメントスタイルこそが、メンバーの自信を奪い、挑戦する意欲を削ぎ、チーム全体の売上を停滞させる最悪のスパイラルなのです。
「こと」に悲観的で、「ひと」に楽観的という、「逆説のマネジメント」
では、成果を出し、メンバーを成長させるマネジャーは、一体何が違うのでしょうか。
答えは、先ほどの思考パターンを、そっくりそのまま180度ひっくり返し、「こと(事柄)に悲観、ひと(人)に楽観」することにあります。
この逆説的なマネジメントが、なぜこれほどまでに強力な効果を発揮するのか、そのメカニズムを解説していきます。
多くのマネジャーが「こと」に楽観的になってしまう理由
それは、身も蓋もないことを言えば、マネジャー自身が、その「こと(商談)」に対して、成果を出すための具体的な指導の引き出しに自信がないからです。
もし、部下から「競合に価格で負けそうです」「決裁者に会えなくて困っています」と相談されたときに、「よし、それならこの3つの方法を試してみよう」と、具体的な打ち手を即座に提示できるマネジャーであれば、商談の状況を悲観的に見積もっても、何も怖くありません。なぜなら、対処法を知っているからです。
しかし、この「引き出し」が少ないマネジャーは、どうなるか。 部下から相談されても、具体的なアドバイスができません。自分で状況をコントロールできる自信がないため、それに正面から向き合うことを避け、「きっとうまくいくさ」と、半ば神頼みのような精神状態に陥ってしまうのです。
そして、祈りが通じず、商談が破談になったとき、「自分には打つ手がなかった」という現実から目をそらすため、「メンバーの能力が足りなかったせいだ」と、責任を転嫁してしまうのです。
「こと」への悲観が、具体的な行動を生む
一方で、「こと」に悲観的なマネジャーは、常に最悪の事態を想定しています。
- 「お客様は『良い』と言っているが、心の底では何を懸念しているだろうか?」
- 「競合は、我々が想像もしないような奇策を打ってくるかもしれない」
- 「この担当者は味方に見えるが、土壇場で裏切られる可能性はないか?」
このように、ありとあらゆるリスク要因を執拗なまでに洗い出し、「そのすべてに、どう対処するか?」を、商談の前にメンバーと徹底的に議論します。このプロセスこそが、営業の精度を極限まで高め、受注確率を劇的に向上させるのです。これは精神論ではなく、極めて実践的なリスクマネジメントです。
「ひと」への楽観が、メンバーの心を強くする
そして、ここからが非常に重要です。 「こと」に対して、これほどまでに悲観的で、厳しい目を向けるマネジャーが、一方で「ひと」に対しては、揺るぎない楽観性を持っているのです。
たとえ、メンバーが準備不足で失敗したとしても、彼らはこう考えます。 「今回の準備は不十分だった。だが、彼自身は素晴らしいポテンシャルを持っている。今回の失敗から学び、次は必ずやり遂げてくれるだろう。私は、彼の人間性を100%信じている」
このスタンスが、メンバーに何をもたらすか。 「マネジャーは、今回の僕の“行動”は叱ったけれど、僕という“人間”のことは信じてくれている」 この絶対的な安心感が、失敗を恐れずに挑戦する勇気を与え、自ら考えて行動する自律的な人材を育てるのです。
「結果を出せ!」が、なぜ最悪の指導なのか
スポーツなどでも言われていることですが、数ある指導方法の中で、「結果を出せというプレッシャー」や「結果が出ないことへの叱責」が、メンバーの成長やモチベーション、そして実際の業績に対しても、ほぼプラスの効果がないことが、統計的に明らかになっています。
「しかし、営業は結果がすべてだろう!」という反論が聞こえてきそうです。おっしゃる通りです。結果を出すことの重要性は、微塵も疑いません。 しかし、
問題なのは、「結果を出すことは重要だ」という事実と、「『結果を出せ』とプレッシャーをかける指導法」とを、混同してしまうことです。後者は、ほとんどの人間にとって、ただの苦痛でしかありません。
「でも、プレッシャーで伸びる人間もいるぞ!」 はい、ごく一部にはいます。
しかし、そういう人たちは、他のどんな有効な指導法(例えば、具体的な作戦会議やスキル指導)を行っても、同じように、あるいはそれ以上に伸びるのです。プレッシャーでしか伸びない人間など、本来は存在しないのかもしれません。
あなたの仕事は、ギャンブルのように、ごく一部の人間にしか効かない「プレッシャー」という劇薬に頼ることではありません。すべての人間に有効な、「具体的な行動レベルでの支援」という、確実な処方箋を提供することなのです。
明日から、あなたの言葉を一つだけ変えてみませんか?
「こと」に悲観的になり、リスクを徹底的に洗い出す。 「ひと」に楽観的になり、その可能性を信じ抜く。
この逆説のマネジメントを、明日から完璧に実践するのは難しいかもしれません。 でしたら、まずは、たった一つ、あなたの言葉を変えることから始めてみませんか。それは、
メンバーを指導する際に、「なぜ?」という詰問を一つ減らし、代わりに「どうすれば?」という作戦会議の質問を一つ増やすことです。
「なぜ、準備が足りなかったんだ?」と言う代わりに、 「このリスクをなくすために、どうすれば万全の準備ができるか、一緒に考えようか?」と聞いてみてください。
この、ほんの小さな言葉遣いの変化が、あなたとメンバーの関係性を劇的に変え、チームの空気を一新し、やがては会社の売上という形で、大きな成果となって返ってくるはずです。
メンバーが自走する「勝てる組織」の作り方
メンバー一人ひとりが、上司からの信頼を背に、自律的に考え、行動し、チームとして最大の成果を出す。そんな「勝てる営業組織」の根幹には、常に正しく、そして力強いマネジメントの哲学が存在します。
もし、
- 部下との関係に悩み、どう指導すれば良いか分からない…
- チームの売上が、特定の個人の頑張りに依存してしまっている…
- メンバーの可能性を最大限に引き出し、持続的に成長する組織を本気で作りたい…
と心から願う経営者、マネジャーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
トレテクでは、単なる精神論ではない、心理学とデータに基づいた科学的なアプローチで、あなたのマネジメントを変革し、組織のポテンシャルを最大限に引き出すお手伝いをします。
まずは、60分間の無料オンライン相談で、貴社が抱える組織の課題や、あなたが目指したい理想のチーム像について、お聞かせください。もちろん、無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。
また、日々のマネジメントに役立つヒントや、強い組織作りの考え方などを、Instagramでも発信しています。こちらも、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。
あなたのマネジメントが、メンバーにとって最高の翼となり、会社を新たな高みへと導くためのお手伝いができる日を、心から楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。