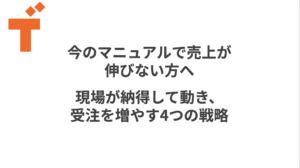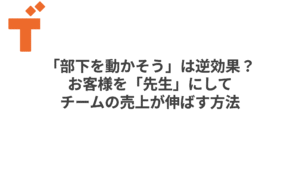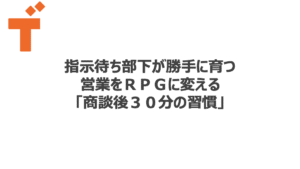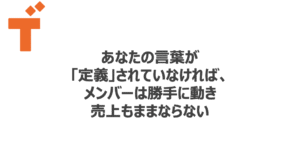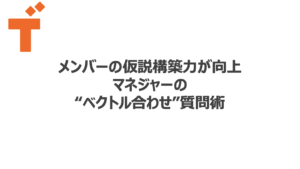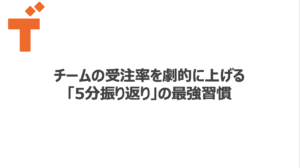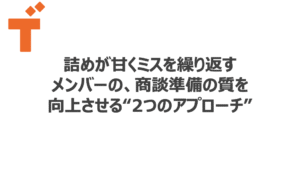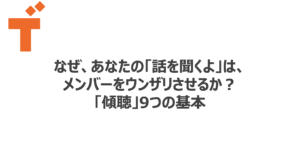部下の成長が加速する“成功確率50%”の法則と、OJTの質を劇的に変える「仕事の分解術」
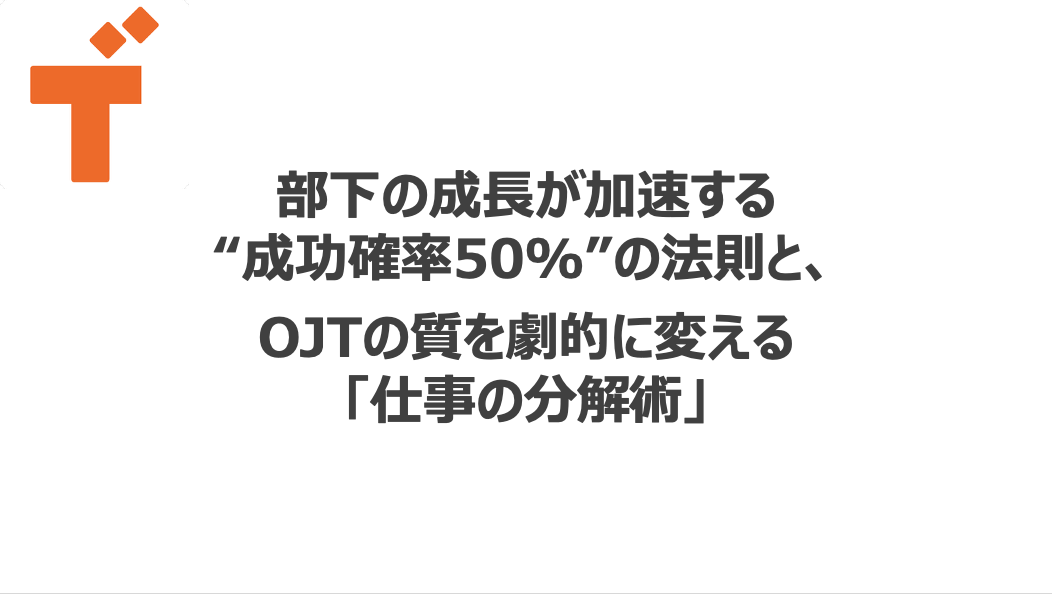
「あとは、君なりに頑張ってみてくれ」
そう言って部下に新しい仕事を任せた後、「本当に、これで育つのだろうか…?」と、漠然とした不安に襲われたことはありませんか?
手取り足取り教える時間はない。しかし、丸投げしても一向に育つ気配はない。良かれと思って難易度の高い案件を任せれば心を折り、かといって簡単な仕事ばかりさせていては成長しない。OJT(On-the-Job Training)とは、なんと厄介で、つかみどころのないものか…。
この記事は、そんな「部下育成」という名の、終わりのない試行錯誤に疲れ果てている、すべての経営者と営業マネージャーのために書きました。
この記事を読めば、その不安の正体がわかり、明日からあなたのOJTを「運任せの育成」から「科学的な育成」へと変貌させる、具体的でパワフルな技術が手に入ります。
あなたのOJTが失敗する、たった一つの理由
なぜ、多くのOJTはうまくいかないのでしょうか。熱意が足りないから? それとも、教えるスキルが低いから?
もちろん、それらも一因かもしれません。しかし、もっと根源的な問題があります。それは、ほとんどのマネージャーが「難易度」という、育成において最も重要な変数を、全くコントロールできていないからです。
多くの現場では、OJTが二つの悲しい極のどちらかに振り切れてしまっています。
失敗例①:いきなり崖から突き落とす「丸投げ地獄」
「俺の背中を見て育て」とばかりに、まだ泳ぎ方も知らない新人に、いきなり太平洋のど真ん中に放り込むような育成法です。運良く生き残る超人が一握り現れるかもしれませんが、大多数は何もできずに自信を失い、静かに会社を去っていきます。
失敗例②:いつまでも自転車の補助輪を外さない「過保護天国」
部下の失敗を恐れるあまり、仕事にことごとく介入し、問題が起きる前にすべて先回りして解決してしまう。部下は楽かもしれませんが、いつまで経っても独り立ちできず、自分で考えて行動できない「指示待ち人間」が完成します。
この両極端な失敗に共通するのは、部下の現在のスキルレベルに対して、与える仕事の「難易度」が全く見合っていない、という点です。そして、この「難易度」こそが、部下の成長のスイッチをONにするか、OFFにしてしまうかを決める、決定的な鍵なのです。
科学が証明した、人が最も成長する「魔法の難易度」
では、どのくらいの難易度が、人の成長にとって最適なのでしょうか。
これについて、心理学者のアトキンソン氏が行った非常に興味深い研究があります。彼は、「人間が“やってみよう”という挑戦意欲が最も高まるのは、一体どんな時か?」を調べました。
その結果、導き出された答えは、驚くほどシンプルでした。 それは、「成功確率が50%の課題」に直面した時です。
言い換えれば、「2回挑戦すれば、1回はうまくいく」くらいの、絶妙な難しさ。これこそが、人間のやる気と成長を最大化する“魔法の難易度”なのです。
考えてみてください。
- 簡単すぎる課題(成功確率90%)では、少しも頭を使わなくてもクリアできてしまうため、新しいスキルを学んだり、工夫したりする必要がありません。ただの「作業」になり、成長は生まれません。
- 難しすぎる課題(成功確率10%)では、「どうせやっても無駄だ」という無力感が先に立ち、挑戦する前から諦めてしまいます。
しかし、成功確率50%の課題は違います。「今の自分のままでは、うまくいくか、いかないか、五分五分だ…。成功するためには、何か新しいやり方を試すか、自分の能力をもう一段階引き上げる必要があるぞ」と、自然と脳が“成長モード”に切り替わるのです。
あなたのOJTは、部下にこの「成功確率50%」の絶妙なチャレンジを提供できているでしょうか?
OJTの本質とは、「観察」と「チューニング」である
「なるほど、50%が大事なのはわかった。でも、どうすればそんな絶妙な難易度の仕事を用意できるんだ?」
そう思われたかもしれません。もちろん、部下に「この仕事、成功確率50%くらいに感じる?」と尋ねても意味はありません。
ここでマネージャーに求められるのが、「観察力」と「チューニング(微調整)能力」です。
部下の仕事ぶりを注意深く観察し、 「お、この仕事は彼にとって簡単すぎるな。見かけ上は目標達成しているが、余裕綽々で、成長が止まっているかもしれない」 と感じれば、難易度を少し引き上げる。
逆に、 「この案件は、彼女にはまだ荷が重すぎたか。ずっと苦しそうな顔で、にっちもさっちもいかなくなっているな」 と感じれば、難易度を少し下げるためのサポートを入れる。
この地道な「チューニング」こそが、OJTの本質なのです。
私が以前、数十人規模のプロジェクト組織で毎年新人を育成していた時、最も心を砕いたのが、この難易度調整でした。
特に、1年目から2年目に上がるタイミングで、一人ひとりのスキルレベルを注意深く見極め、「今の君にとって、最高のチャレンジになるはずだ」という案件を、先輩から引き継ぐ形で1社ずつ担当させたのです。
その結果は、劇的でした。それまでの画一的な育成方法と比べ、メンバーの成長スピードが格段に上がったのです。
経験から考えても、「ただ経験年数を重ねるだけではスキルは上がらない」「ダメ出しや叱責は成長に全くインパクトがない」ことは明らかです。意図的に設計された「ちょうどいい難易度」の経験こそが、人を育てるのです。
究極の難易度調整術、それが「仕事の分解」
しかし、多くの営業組織の現実は、「仕事が難しすぎる」というケースの方が多いでしょう。次々と高い目標が課され、メンバーが疲弊している。
そんな時、どうやって難易度を「成功確率50%」に近づければいいのでしょうか。 「代わりにやってあげる」のは過保護。「自分でやれ」と突き放すのは丸投げ。
このジレンマを解決する有効な技術が、「仕事の分解」です。
どんなに複雑で巨大に見える仕事も、必ず複数の小さなタスクの集合体です。その仕事を小さな工程に「分解」し、それぞれの工程ごとに、マネージャーの関与度を変える。これこそが、最も高度で効果的な難易度調整術なのです。
例えば、若手メンバーが「お客様への提案書作成」に苦戦しているとしましょう。
ここで、「全部自分で考えてみろ」でも、「はい、俺が作っておくよ」でもなく、まず、この「提案書作成」という仕事を、以下のように分解してみるのです。
- 工程①:お客様の課題と要望を整理する(要件整理)
- 工程②:提案の全体像とストーリーを作る(構成作成)
- 工程③:構成に沿って、各スライドのメッセージを考える(内容考案)
- 工程④:既存の資料などを参考に、スライドを作成する(資料作成)
- 工程⑤:完成した資料を、声に出してプレゼンの練習をする(実践練習)
そして、それぞれの工程に対して、こうチューニングしていくのです。
「よし、まず工程①の要件整理は、認識がズレると大変だから、一緒に壁打ちしながらやろう」 「工程②の構成は、一番難しいから、たたき台は俺が作って渡すよ」 「工程③と④は、その構成に沿って、まず君一人でやってみてくれないか。難しいスライドが出てきたら、その部分だけ相談に乗るから」 「そして、工程⑤の練習は、俺がお客様役になるから、一度聞かせてくれ」
いかがでしょうか。 一つの大きな塊だった「提案書作成」という仕事が、「一緒にやるパート」「任せるパート」「サポートするパート」に分解され、全体の難易度が「少し頑張ればできそう」なレベルに調整されているのがお分かりいただけると思います。
これが、「仕事を分解する力」がOJTの質を左右する、ということです。
まずは「苦戦している仕事」を5つのステップに分解してみよう
あなたのOJTを、今日から変えてみませんか。 難しい理論は必要ありません。まずは、たった一つのアクションから始めてみてください。
あなたの部下が今、一番苦戦している仕事を一つ、思い浮かべてください。そして、その仕事を“5つの小さなステップ”に分解して、紙に書き出してみるのです。
それだけで、あなたがどこを支援し、どこを任せるべきかの「OJT設計図」が、驚くほどクリアに見えてくるはずです。その設計図こそが、運任せの育成から脱却し、部下を着実に成長へと導く、最初の羅針盤となります。
「教える」から「成長環境を設計する」へ
OJTとは、単に仕事のやり方を「教える」ことではありません。部下一人ひとりのスキルレベルを見極め、彼らが最も成長できる「環境を設計する」という、高度なマネジメント技術です。
もし、
- 自社のOJTが場当たり的になっており、体系化できていない…
- 部下の成長スピードにバラつきがあり、育成方法に悩んでいる…
- 感覚的な指導から脱却し、科学的根拠に基づいた“育成の仕組み”を構築したい…
と、本気でお考えの経営者、マネージャーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
トレテクは、貴社の業務内容とメンバーのスキルレベルを詳細に分析した上で、この「難易度調整」と「仕事の分解」の考え方をベースにした、再現性の高いOJTプログラムを設計します。
まずは60分の無料オンライン相談で、貴社が抱える人材育成の課題について、お話をお聞かせください。無理な勧誘は一切ございませんので、どうぞご安心ください。
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。こちらも、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。
あなたのその「分解する力」が、部下の可能性を最大限に引き出し、ひいては会社全体の成長を加速させる最強の武器になります。その武器を手に入れるお手伝いができることを、心から楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。