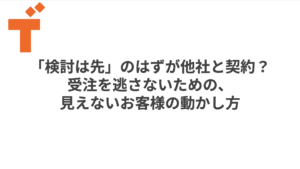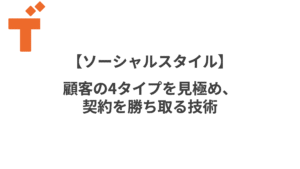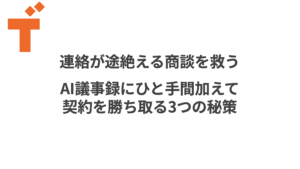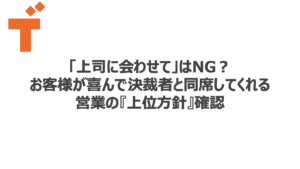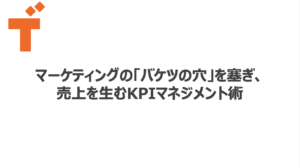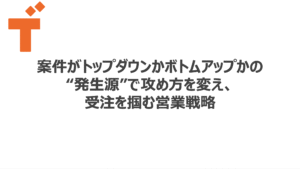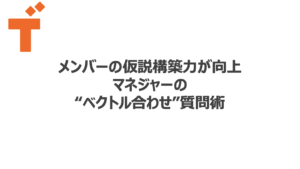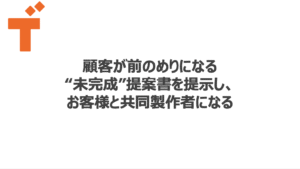“聞く”という行為の根本的な意味を理解し、営業に活かす
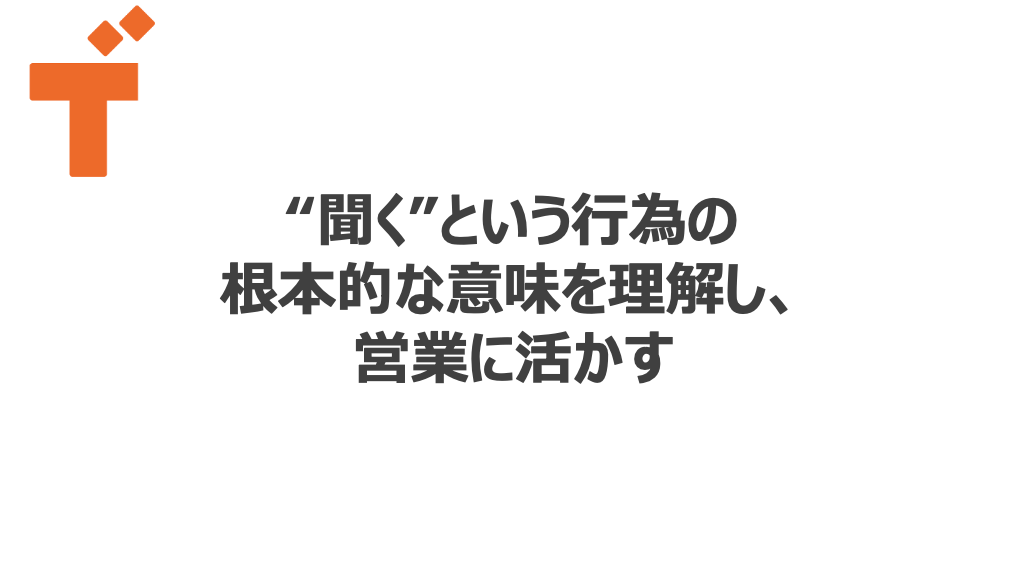
「人の話をよく聞きなさい」
私たちは子供の頃から、親や先生にそう教わってきました。そして、ビジネスの世界、特に営業やマネジメントの現場でも、「傾聴力(けいちょうりょく)」「ヒアリング力」の重要性は、嫌というほど聞かされているはずです。書店に行けば、「聞く技術」「聴く力」といったタイトルの本が、それこそ山のように平積みされています。
でも、ここで少し立ち止まって考えてみませんか? そもそも、なぜ「聞く」ことは、それほどまでに重要なのでしょうか?
多くのハウツー本は、「聞くことは良いことだ」という“大前提”のもと、相槌(あいづち)の打ち方や質問の仕方といった具体的な「テクニック」を教えてくれます。
しかし、「なぜ、それらのテクニックが必要なのか?」「『聞く』という行為の、もっと根本的な意味は何なのか?」という、本質的な問いに答えてくれるものは、意外と少ないように感じます。
このコラムでは、単なる営業テクニックとしての「聞き方」ではなく、人間の「認識」や「対話」の本質にまで踏み込みながら、なぜ「聞く(聴く)」ことが、私たちのビジネス、ひいては人生において、計り知れない価値を持つのかを解き明かしていきたいと思います。
この記事を読み終える頃には、「聞く」という行為に対するあなたの見方が、大きく変わっているかもしれません。そして、明日からの営業活動や経営判断において、驚くほどの変化を実感できるはずです。
貴社の営業力を飛躍させる「実践型」コンサルタント
ベンチャー・大企業合わせて約20年以上営業現場経験を武器に、貴社に再現性のある「売れる仕組み」を構築します。
現在も営業職として現場の泥臭さを経験しているからこその営業視点を強みとして、座学研修のほか、今日からすぐに使える実践的なノウハウで、特に商談・プレゼン力の向上に貢献します。
「売上を伸ばしたいが、何から手をつければ…」とお悩みの経営者・営業部長様へ、実践型コンサルティングで、貴社の営業チームを強化し、確かな成果へと導きます。

「聞いてるつもり」なのに、なぜか話が噛み合わない…
「ちゃんとお客様の話を聞いているはずなのに、どうも話が噛み合わない」
「良かれと思って提案したのに、『いや、そういうことじゃないんだよ…』と、お客様に怪訝(けげん)な顔をされてしまう」
「部下の育成のために、時間を取って面談しているのに、どうも本音を引き出せていない気がする…」
営業の最前線で奮闘されている方、あるいはチームを率いる立場の経営者や営業マネージャーの方なら、一度はこんな壁にぶつかった経験があるのではないでしょうか?
私自身、新人営業時代に、苦い経験があります。ある重要なお客様との商談で、自分なりに一生懸命お客様の話を「聞いて」いるつもりでした。メモを取り、適度に相槌を打ち、時折質問も投げかける…。
しかし、商談が進むにつれて、どうもお客様の表情が曇っていくのです。最終的に、お客様から「君は…本当に私の話を理解しようとしてくれている?」と、静かに、しかし厳しい口調で問われてしまいました。
当時の私は、「聞いている」つもりで、実は「自分の言いたいことを言うために、話の着地点を探していた」だけだったのです。相手の話を批判的に聞き、矛盾点を見つけ、どう反論しようか、どう自分の提案に繋げようか、ということばかり考えていました。
また、ある経営者の方からは、こんな悩みを聞いたことがあります。「社員の声を聞こうと、定期的にミーティングを開いているんだが、どうも活発な意見交換にならない。結局、私ばかりが話してしまって、社員たちは黙って聞いているだけ。彼らが本当は何を考えているのか、さっぱり分からないんだ…」
「聞く」という行為は、日常的に行っているだけに、その難しさ、奥深さが見過ごされがちです。しかし、この「聞く力」の欠如が、営業成績の伸び悩み、チーム内のコミュニケーション不全、ひいては経営判断の誤りといった、深刻な問題を引き起こす原因となっているケースは、決して少なくないのです。
私たちは「自分だけの映画」を見ている
さて、なぜ「聞く」ことがこれほどまでに重要なのか、その本質に迫るために、まずは「人間がどのように世界を認識しているのか?」という、少し哲学的な話から始めましょう。難しく考える必要はありません。きっと、あなたのビジネスにも直結する、重要なヒントが見つかるはずです。
古今東西の偉大な哲学者たちは、口を揃えて、人間の「認識」について、非常に興味深いことを言っています。
「人間は考える葦(あし)である」(パスカル)
「我思う、ゆえに我あり」(デカルト)
「我々は世界をありのままに見ていない。認識というフィルターを通して見ている」(カント)
「真実などない。あるのは認識だけだ」(ニーチェ)
一見、難しい言葉が並んでいますが、彼らが言わんとしていることは、実は非常にシンプルです。それは、「私たちが『現実』だと思っているものは、実は、自分の頭の中で作り上げられたものだ」ということです。
もっと現代的な言葉で表現するなら、私たちは、外側の客観的な現実を直接見ているのではなく、自分の「頭蓋骨(ずがいこつ)の内側にあるスクリーン」に映し出された、いわば「自分だけの映画」を見て生きている、と言えるでしょう。
目や耳から入ってきた情報は、そのまま直接、私たちの意識に届くわけではありません。それらは、私たちの脳の中にある、これまでの経験、知識、価値観、好き嫌い、思い込みといった、無数の「フィルター」を通過します。
そして、それらのフィルターによって解釈され、編集され、意味付けされたものが、最終的に「映画」として、私たちの頭の中のスクリーンに映し出されるのです。私たちは、その「映画」を見て、「これが現実だ」と認識し、日々の判断や行動を行っているわけです。
ここで最も重要なポイントは、同じ出来事を経験しても、人によって頭の中に映し出される「映画」は、全く違うものになる、ということです。
例えば、「雨が降ってきた」という、ごく単純な現象を考えてみましょう。
ある人にとっては、「あーあ、洗濯物が濡れちゃうな。傘を持ってくるんだった。雨は嫌いだ」というネガティブな感情を伴う「映画」が映し出されるかもしれません。
しかし、農家の人にとっては、「恵みの雨だ!これで畑の作物が元気に育つぞ。ありがたいな」というポジティブな感情を伴う「映画」になるかもしれません。
あるいは、恋人と相合傘ができるのを楽しみにしている人にとっては、ロマンチックな「映画」に映るかもしれませんし、インドア派の人にとっては、「これで心置きなく家で読書ができる」という、静かで穏やかな「映画」になるかもしれません。
「雨が降る」という客観的な事実は一つでも、それを受け止める人のフィルターによって、無数の異なる「主観的な現実(映画)」が生成されるのです。
営業の場面でも、経営の場面でも、この「人によって見ている映画が違う」という大原則を理解しておくことは、コミュニケーションの齟齬(そご)を防ぐ上で、決定的に重要になります。
「群盲象を撫でる」寓話が教える、部分理解のワナ
この「人によって見ている世界が違う」ということを、実に巧みに表現した、有名なインドの古い寓話(ぐうわ)があります。「群盲象(ぐんもうぞう)を撫(な)でる」という話です。ご存知の方も多いかもしれませんね。
目が見えない複数人の賢者たちが、生まれて初めて「象」という生き物に触れる機会を得ました。彼らは、それぞれ象の異なる部分を触り、そして、自分たちが触った感触をもとに、「象とは何か?」を語り始めます。
耳を触った賢者は言いました。「なるほど、象というのは、まるで王様が使う大きなうちわのようなものだな」
鼻を触った賢者は言いました。「いやいや、象とは、しなやかで力強い、大蛇のような生き物に違いない」
尻尾を触った賢者は言いました。「ふむ、象とは、細くて丈夫な、ロープのようなものらしい」
足を触った賢者は言いました。「何を言うか。象とは、どっしりとした大木の幹のようなものだぞ」
さて、彼らの言っていることは、それぞれ「間違って」いるでしょうか? いいえ、自分が触った部分に関しては、彼らの表現は「正しい」のかもしれません。耳はうちわのようですし、鼻は大蛇のようにも感じられるでしょう。
しかし、彼らの語る「象」は、象という生き物の全体像を表しているでしょうか? 残念ながら、そうではありません。彼らはそれぞれ、象の一部分だけを捉えて、それが全体であるかのように語っているに過ぎません。まさに「間違ってはいないけれど、正しくもない」状態です。
この寓話は、私たちに非常に重要な教訓を与えてくれます。私たちは、往々にして、自分の限られた経験や知識(自分が触った部分)に基づいて、物事の全体像を判断してしまいがちだ、ということです。
これは、ビジネスの現場でも、日常的に起こっていることです。例えば、ある会社の「新しいビジョン」について話し合っているとしましょう。
経営者は、「会社の持続的な成長と社会貢献」という視点からビジョンを語るかもしれません。(象の全体を見ているつもり?)
営業部長は、「短期的な売上目標の達成と市場シェアの拡大」という視点で解釈するかもしれません。(象の力強い足?)
開発部長は、「革新的な技術の開発と製品の品質向上」という視点で捉えるかもしれません。(象の器用な鼻?)
現場の若手社員は、「自分のスキルアップと働きがい」という視点で見ているかもしれません。(象の尻尾?)
それぞれが、同じ「会社の目指すべき方向」というテーマについて語っているつもりでも、その背景にある価値観や経験、立場(見ている「映画」)が異なるため、微妙に、あるいは全く異なる解釈をしてしまう。
その結果、「我が社は、青い海を目指すべきだ!」「いや、緑の山に決まっている!」といった、認識のズレが生じ、組織としてのベクトルが合わず、チームがバラバラに動いてしまう…そんな事態を招きかねないのです。
「聞く」ということは、相手が象のどの部分を触って、それをどのように感じているのか、つまり、相手の「部分的な真実」とその背景にある「映画」を理解しようと試みることに他なりません。
対話とは「議論」ではなく「景色合わせ」である
では、このように、それぞれが違う「映画」を見て、違う「象の捉え方」をしている私たちが、どうすれば建設的なコミュニケーションを取り、互いを理解し、協力していくことができるのでしょうか?
その鍵を握るのが「対話」です。
しかし、ここで言う「対話」とは、単に「話し合う」ことではありません。ましてや、自分の意見を主張し合い、相手を論破しようとする「議論(ディベート)」とは、全く異なります。
対話の本質は、「事柄」そのものではなく、その事柄に対する相手の「見方」や、その見方の背景にある「感情」や「価値観」を、互いに聞き合い、理解しようと努めることにあります。
なぜ、相手はそう考えるのか? なぜ、相手はそう感じるのか? 相手の頭の中のスクリーンには、どんな「映画」が映し出されているのか?
この「なぜ?」に焦点を当て、相手の内面の世界、つまり相手が見ている「景色」を理解しようとする姿勢こそが、対話の出発点なのです。
オーケストラが美しいハーモニーを奏でるためには、演奏を始める前に、必ず「チューニング(音合わせ)」を行いますよね? それぞれの楽器が、基準となる音(例えば、A=ラ の音)に自分の音を合わせることで、初めて調和のとれた音楽が生まれます。
対話も、これと全く同じです。自分の主張(自分の楽器の音)を一方的に奏でる前に、まずは相手がどんな「景色(音)」を見ている(奏でている)のかに、注意深く耳を傾け、理解しようと努める。
そして、お互いの「景色」を照らし合わせ、共有していく。この「景色合わせ」のプロセスこそが、真の対話なのです。
そのためには、相手の話に対して、純粋な「興味・関心」を持つことが不可欠です。
「この人は、なぜこんなことを言うのだろう?」「どんな経験をしてきたから、こういう考え方になったのだろう?」と、まるで未知の世界を探検するような好奇心を持って、相手の話に耳を傾ける。
そして、言葉だけでなく、表情や声のトーンといった非言語的な情報も手がかりにしながら、相手の「映画」を想像してみる。この「興味」と「想像力」こそが、「景色合わせ」を成功させるための重要なエンジンとなります。
最近、マレーシアやシンガポールといったアジアの指導者たちが、複雑な国際問題(例えば、台湾と中国の緊張関係)について語る際、「対話」の重要性を繰り返し強調しているのが印象的です。
マレーシアの建国の父と言われるマハティール氏も、「すべての問題は、対立ではなく、対話によって解決されるべきだ」と述べています。彼らの言う「対話」とは、まさに、互いの立場や背景を理解しようと努める「景色合わせ」のプロセスを指しているのでしょう。
「いかにうまく伝えるか」ではなく、「いかに深く理解するか」。 そして、「理解してから、理解される」。この順番を間違えないことが、営業においても、経営においても、あらゆる人間関係において、決定的に重要なのです。
「弁証法」に学ぶ、対立から新しい価値を生み出す力
対話を通じて、互いの「景色」の違いが見えてくると、そこには当然、「意見の対立」が生まれることもあります。Aという考えを持つ人と、Bという考えを持つ人。
お互いが「自分こそが正しい!」と主張し合えば、平行線をたどるか、せいぜい、どちらも不満が残る「妥協点」を見つけるくらいしかできません。
しかし、ここで「対話」の真価が発揮されます。ドイツの哲学者ヘーゲルが提唱した「弁証法(べんしょうほう)」という考え方が、ヒントを与えてくれます。難しく聞こえるかもしれませんが、これも考え方はシンプルです。
弁証法とは、
まず、ある「主張(テーゼ)」があります。(例:「我が社は、品質重視でいくべきだ!」)
それに対して、「反対の主張(アンチテーゼ)」が現れます。(例:「いや、今はスピードと価格が重要だ!」)
この二つの対立する主張を、どちらか一方を否定するのではなく、両方の良いところを取り込み、より高い次元で統合した、新しい「結論(ジンテーゼ)」を生み出す。(例:「品質を維持しつつ、効率化によってスピードと価格競争力を両立させる方法はないだろうか?」)
という、思考のプロセスです。人類の歴史は、まさにこの弁証法のプロセス、つまり、対立する意見のぶつかり合いの中から、より良い、新しい価値(ジンテーゼ)を生み出し続けることで、進化・発展してきた、と言っても過言ではありません。
ポイントは、対立を「悪」と捉えるのではなく、新しい価値を生み出すための「エネルギー源」と捉えることです。そして、そのエネルギーを建設的なジンテーゼへと昇華させるために不可欠なのが、「相手の主張(アンチテーゼ)の背景にある『景色』を、深く『聞く』こと」なのです。
営業の場面で考えてみましょう。
営業(あなた)の主張(テーゼ)は、「この商品/サービスは素晴らしいので、ぜひ導入してほしい!」です。しかし、 お客様の主張(アンチテーゼ)は、「いや、今のままで十分だ」「コストがかかりすぎる」「導入が面倒だ」かもしれません。
ここで、あなたがお客様のアンチテーゼの背景にある「景色」(なぜコストを懸念するのか? 過去に導入で失敗した経験があるのか? 担当者が忙しくて時間が取れないのか?)を深く聞かずに、自分のテーゼばかりを押し付けたらどうなるでしょう? おそらく、交渉は決裂するか、値引き合戦のような不毛な消耗戦になるだけです。
しかし、もしあなたが、お客様のアンチテーゼに真摯に耳を傾け、その背景にある「景色」を理解しようと努めたなら?
そこから、「お客様の懸念(コスト、手間)を解消しつつ、商品の価値(効率化、売上向上)を最大限に享受できるような、新しい提案(ジンテーゼ)」を生み出すことができるかもしれません。例えば、段階的な導入プラン、費用対効果の具体的なシミュレーション、導入サポートの充実などです。
このように、「聞く」ことは、単に対立を避けるためだけではなく、対立の中から、より高い次元の創造的な解決策(ジンテーゼ)を生み出すための、必要不可欠な土台となるのです。
これは、企業間の交渉だけでなく、社内の部門間対立の解消や、新しい事業アイデアの創出など、あらゆる場面に応用できる、強力な思考ツールと言えるでしょう。
「聞いてもらう」ことで、話している相手の中に「答え」が生まれる
ここまで、「相手を理解するために聞く」ことの重要性についてお話ししてきました。しかし、「聞く」ことの力は、それだけではありません。
実は、「真剣に聞いてもらう」という体験そのものが、話している相手の中に、新たな「気づき」や「答え」を生み出すという、驚くべき効果を持っているのです。
コミュニケーションには、通常、「話し手」と「聞き手」がいます。そして、多くの場合、話し手が情報を伝え、聞き手がそれを受け取って「なるほど、そうか!」と理解が深まる、というプロセスを想像しますよね。これは、いわゆる「ティーチング(教える)」のモデルです。
しかし、もう一つ、非常に重要なコミュニケーションのパターンがあります。それは、話し手が話しているうちに、聞き手がただ真剣に耳を傾けているだけで、話し手自身の中に「あっ、そうか!」という「気づき」が生まれる、というケースです。
あなたにも、誰かに悩みや考えを話しているうちに、頭の中が整理されたり、自分でも思いがけなかったアイデアが浮かんできたりした経験はありませんか?
あれは、聞き手が何か特別なアドバイスをしてくれたから、というよりも、ただ黙って、真剣に、共感的に話を聞いてくれたからこそ、起こった現象なのかもしれません。
これは、「コーチング」と呼ばれるアプローチの核心でもあります。優れたコーチは、答えを教える(ティーチング)のではなく、クライアント(話し手)の話を深く「聞く」こと、そして効果的な「質問」を投げかけることを通じて、クライアント自身の中から「気づき」や「答え」を引き出す手助けをします。
なぜ、「聞いてもらう」だけで、そんなことが起こるのでしょうか?
その鍵は、人間の「意識」と「無意識」の関係にありそうです。私たちが普段「意識」している情報や知識は、実は、私たちが持っている情報全体のごく一部に過ぎない、と言われています。その背後には、意識の何万倍、あるいは数百万倍とも言われる、膨大な「無意識」の情報が眠っているのです。
「気づき」とは、この広大な無意識の領域に眠っていた情報やアイデアが、何かのきっかけで、ふっと意識の表面に浮かび上がってくる現象、と考えることができます。
では、どんな時に、この「気づき」は起こりやすいのでしょうか?
三上:「良いアイデアが浮かぶ場所」
面白いことに、昔から「良いアイデアが浮かぶ場所」として知られている場所があります。中国、宋の時代の随筆家、欧陽脩(おうようしゅう)は、それを「三上(さんじょう)」という言葉で表現しました。
「馬上(ばじょう)・枕上(ちんじょう)・廁上(しじょう)」、つまり、馬の上(移動中)、枕の上(寝ようとしている時)、トイレの上(用を足している時)だと言うのです。
現代に置き換えれば、乗り物での移動中、ベッドの中、お風呂やトイレ、といったところでしょうか。千年経っても変わらないこれらの場所には、共通点があります。
それは、リラックスしていて、何かに集中しているわけではなく、心が自由になっている状態だということです。こういう時に、無意識の扉が開きやすくなり、思わぬ「気づき」が訪れるのかもしれません。
化学者ケクレが、夢の中で蛇が自分の尻尾を噛むのを見て、ベンゼン環の構造を発見したという逸話や、発明王エジソンが、うたた寝中に鉄アレイを落とす仕組みを使って、ひらめきを得ようとしたという話も、この「リラックスした状態」と「無意識からの気づき」の関係を示唆しています。
そして、ここからが重要なのですが、この「三上」と同等か、あるいはそれ以上に、「気づき」を促す効果的な方法があります。それが、「誰かに、自分の話を真剣に聞いてもらうこと」なのです。
信頼できる相手に、自分の考えや悩みを、評価や批判を恐れることなく、安心して話せる。聞き手は、ただ黙って、共感的に耳を傾けてくれる…。
そんな「安全な場」で話をしていると、心がリラックスし、思考が整理され、自分でも気づいていなかった無意識下の想いやアイデアが、自然と意識上に浮かび上がってくる。これが、「聞いてもらう」ことによって「気づき」が生まれるメカニズムだと考えられます。
営業として、お客様の話を真剣に聞くことは、お客様のニーズを理解するためだけでなく、お客様自身の中に、新たな課題認識や、商品・サービスへの欲求といった「気づき」を生み出すきっかけにもなり得ます。
また、経営者やマネジャーとして、部下の話をただ真剣に聞くことは、彼らの中に主体性や問題解決能力といった「気づき」を促し、潜在能力を引き出す上で、極めて有効なアプローチとなるのです。
ワンオンワンミーティングや日々の声かけの中で、この「聞く(聴く)」ことによるコーチング効果を意識することは、組織全体の活性化に繋がるでしょう。
あなたが明日からできる「小さな一歩」
さあ、あなたも「聞く(聴く)」ことの力を、明日から試してみませんか? 難しく考える必要はありません。まずは、こんな「小さな一歩」から始めてみてください。
明日の社内会議やお客様との打ち合わせで、誰か一人が発言している間、意識して、自分の「反論」や「意見」を言うのを、ほんの少しだけ待ってみる。
そして、その代わりに、「なぜ、この人は、今、こう言っているのだろう?」「この発言の背景には、どんな想いや経験があるのだろう?」と、相手の「映画(景色)」を、心の中で想像してみる。
ただ、それだけです。 すぐに意見を言いたくなる衝動を抑え、ほんの数秒でも、相手の「内側の世界」に意識を向けてみる。この小さな習慣が、あなたのコミュニケーションの質を、確実に変え始めるはずです。
まとめ:「聞く」ことは、未来を創造する力である
「聞く」という行為は、単なるコミュニケーションの入口ではありません。それは、
私たちがそれぞれ違う「主観的な世界(映画)」に生きていることを理解するための「窓」であり、
「群盲象を撫でる」ような部分的な理解から脱却し、全体像を捉えるための「羅針盤」であり、
対立する意見の中から、より良い未来(ジンテーゼ)を創造するための「触媒」であり、
そして、相手の中にある無限の可能性(無意識の気づき)を引き出すための「鍵」なのです。
営業として、お客様の真のニーズを掘り起こし、信頼関係を築くために。 経営者やマネジャーとして、多様な意見をまとめ上げ、組織の創造性を最大限に引き出すために。 そして、一人の人間として、他者と深く理解し合い、豊かな人間関係を育むために。
この「聞く(聴く)力」は、間違いなく、あなたのビジネスと人生を、より豊かで実りあるものにしてくれる、最もパワフルなスキルの一つです。
今日、このコラムでお伝えした「聞くことの本質」を、ぜひ、日々の現場で意識し、実践してみてください。きっと、これまでとは違う景色が見えてくるはずです。
「聞く力」を、単なる個人のスキルとしてだけでなく、組織全体の「文化」として根付かせたい。そうお考えの経営者、営業マネジャーの方へ。
貴社の具体的な課題や目標に合わせて、「聴く力」を基盤とした営業力強化プログラムや、組織開発コンサルティングをご提供しています。心理学や脳科学の知見も取り入れた、実践的かつ効果的なアプローチで、貴社の変革をサポートします。
まずは、60分間の無料オンライン相談で、あなたの悩みや目指したい姿をお聞かせください。無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。下記のリンクから、今すぐ無料相談にお申し込みいただけます。
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。よろしければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。
あなたの、そして貴社の営業が、お客様から心から信頼され、選ばれ続ける存在になるためのお手伝いができることを、楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。