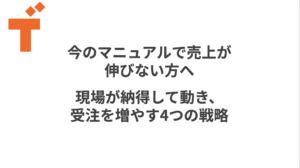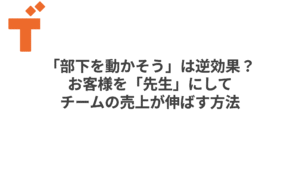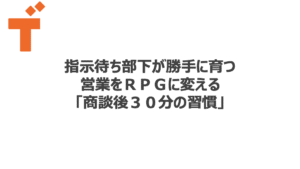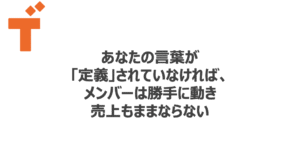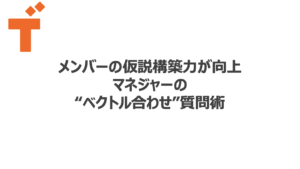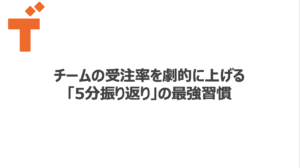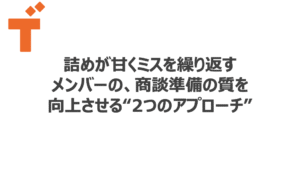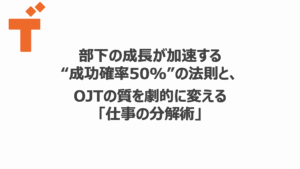「褒めないと部下が辞める」は本当か?売上を伸ばす営業が育つ「自分軸」育成の黄金律
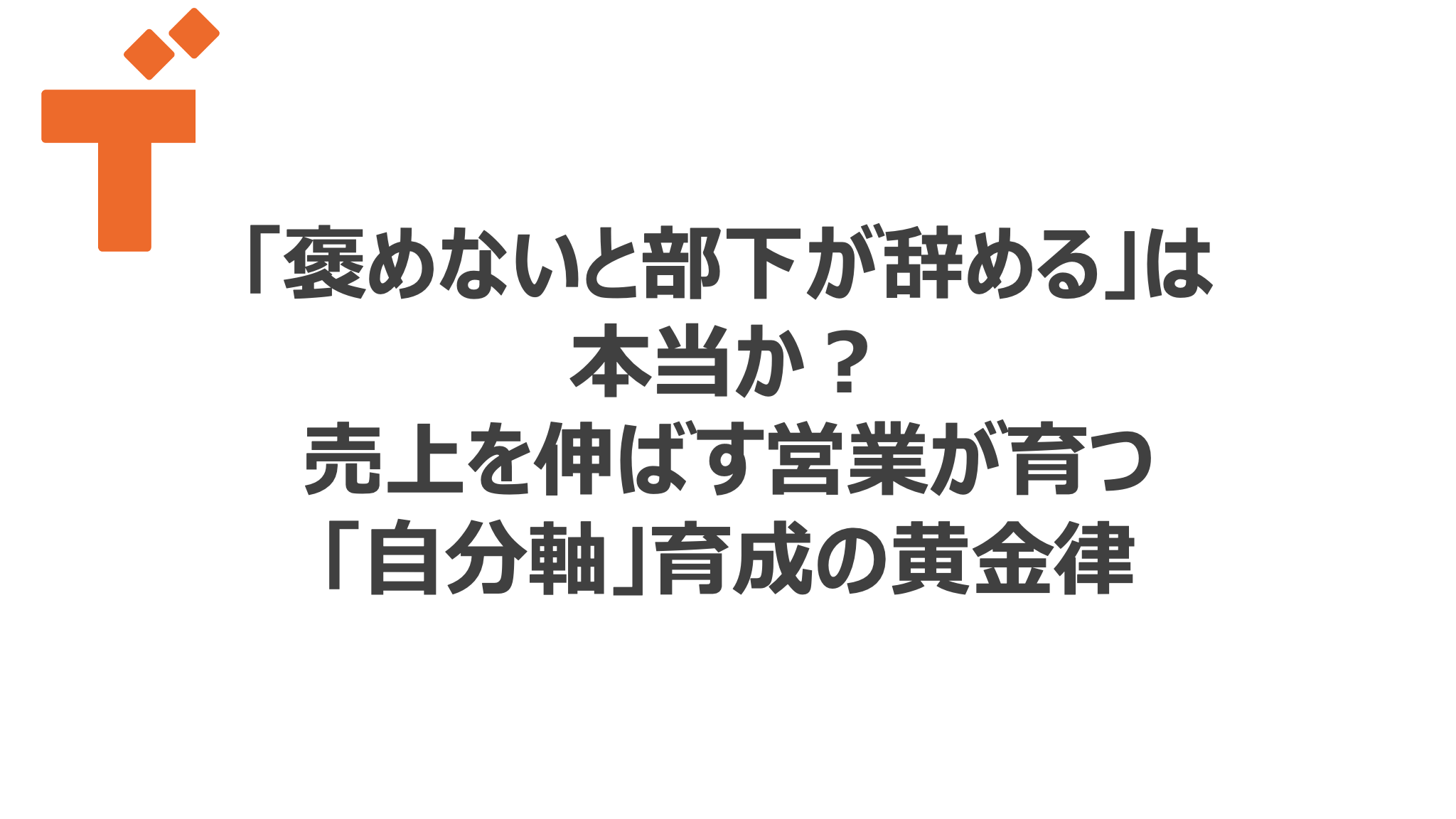
「最近の若手は、本当に打たれ弱いな…」
「褒めても褒めても、なかなか自信が持てないし、すぐに他人の評価を気にする…」
「いったい、どうすれば部下は自律的に成長し、売上に貢献してくれるようになるんだ…?」
経営者として、あるいは営業マネジャーとして、部下の育成に関してこんな悩みを抱えて夜も眠れない、なんてことはありませんか?
良かれと思って導入した「褒める教育」。しかし、それが逆に部下の主体性を奪い、あなたの会社の将来を担うべき営業パーソンの成長を妨げているとしたら…。
この記事では、現代の育成における大きなテーマである「褒める教育」の知られざる落とし穴と、他人の評価に一喜一憂することなく、自らの足でしっかりと立ち、困難な状況でも粘り強く受注できる「真の強さ」を持った人材を育むための本質について、深く、そして具体的に掘り下げていきます。
貴社の営業力を飛躍させる「実践型」コンサルタント
ベンチャー・大企業合わせて約20年以上営業現場経験を武器に、貴社に再現性のある「売れる仕組み」を構築します。
現在も営業職として現場の泥臭さを経験しているからこその営業視点を強みとして、座学研修のほか、今日からすぐに使える実践的なノウハウで、特に商談・プレゼン力の向上に貢献します。
「売上を伸ばしたいが、何から手をつければ…」とお悩みの経営者・営業部長様へ、実践型コンサルティングで、貴社の営業チームを強化し、確かな成果へと導きます。

褒めても、叱っても…なぜか部下指導が空回りする“現代のリアル”
「最近の若いもんは…」と、紋切り型で若者論を語るつもりは毛頭ありません。しかし、部下指導の現場で、かつての常識が通用しなくなっている、と感じる経営者やマネージャーの方は少なくないのではないでしょうか。
例えば、少し厳しくフィードバックをしただけで、翌日から会社に来なくなってしまった…なんて話も、残念ながら耳にします。
かといって、腫れ物を触るように、ただただ褒めちぎって育ててみても、今度は「褒められるのが当たり前」になってしまい、少しでも称賛の言葉がないと「自分はダメなんだ…」と勝手に自己評価を下げてしまう。
あるいは、常に「上司はどう思うだろうか」「周りからどう見られるだろうか」と、他人の顔色ばかりをうかがうようになってしまう。
これでは、いくら手厚く営業研修を施しても、お客様の厳しい要求に応え、プレッシャーのかかる場面で契約をまとめ上げなければならない営業の現場で、本当にタフに戦い抜ける人材は育ちません。
チーム全体の売上目標を達成することも、夢のまた夢となってしまいます。
この、なんともやりきれない部下指導の「空回り感」。その根源には、実は「褒める」とか「叱る」といった表面的なテクニック以前の、もっと根深い問題が横たわっているのかもしれません。
なぜ「褒める教育」だけではダメなのか? 知られざる“副作用”
まず、現代の教育や人材育成の主流となりつつある「褒める教育」について考えてみましょう。「部下の自己肯定感や自己効力感を高めるためには、とにかく褒めて伸ばすのが良い」という考え方ですね。
「お前はダメだ」「何をやっているんだ!」と頭ごなしに怒鳴りつけて自信を失わせるよりは、確かに建設的に聞こえます。
しかし、ここに大きな落とし穴があると、ある教育業界の知人は警鐘を鳴らします。彼曰く、最近の子供たちは、学校でも家庭でも「怒られる」という経験が極端に少ないため、いざ社会に出て、あるいは少し厳しい指導者に遭遇して叱責された途端、極度なアレルギー反応を起こし、心がポッキリ折れてしまうケースが後を絶たない、というのです。
まるで、無菌状態で育ったために、ちょっとした雑菌にも抵抗できなくなってしまったかのように。
さらに深刻なのは、「褒める教育」一辺倒で育った結果、逆に「褒められない」という状況に対して、極めて脆弱になってしまうという皮肉な現実です。
本来、他人から褒められようが褒められまいが、自分の価値は変わらないはず。つまり、「褒められない」という状況は、プラスマイナスゼロであるべきです。
しかし、「常に褒められること」を栄養にして育ってきた人は、いざ褒められない状況に直面すると、「あれ?褒めてくれないの?」「もしかして、自分はダメなのかな…?」「もう、やる気なくなった…」と、勝手に自分でマイナスの評価を下し、自信を失ってしまうというのです。
これでは、自己肯定感を高めるために行っていたはずの「褒める教育」が、結果的に、他人の評価に自分の価値を委ねてしまう「他人軸でブレブレ」な人間を生み出していることになりかねません。褒めてくれなければ不安になる、褒めてくれなければ頑張れない…。
これは、子供の世界だけでなく、驚くほど多くの社会人、それもいい大人にまで見られる現象だと、私は感じています。
もちろん、他人から褒められれば嬉しいし、怒られれば誰だって落ち込みます。それは人間として自然な感情です。しかし、その感情に自分の存在価値そのものが揺さぶられてしまうのだとしたら、それは非常に危険な状態と言えるでしょう。
育成の鍵は「振れ幅への慣れ」と「自分軸の確立」にあり!
では、どうすれば、他人の評価に振り回されず、自らの力で道を切り拓いていけるような、真に強い人材を育てることができるのでしょうか? 私は、そこに2つの重要な要素があると考えています。
1.「感情の振れ幅」に慣れさせる ~ プラスとマイナスの両極を知る勇気
まず一つ目は、「感情の振れ幅」に慣れることの重要性です。
人間が生きていれば、褒められて有頂天になる日もあれば、叱られてどん底まで落ち込む日もあります。それはまるで、温度計の針がプラスにもマイナスにも大きく振れるようなもの。
この「プラスの温度」と「マイナスの温度」の両方を経験し、その振れ幅に精神的に慣れていくこと、いわば「心の耐熱性・耐寒性」を鍛えることが、非常に重要だと私は考えます。
もし、「怒られること」だけを経験し続ければ、その人の心の温度計は、常にマイナス100度からプラマイゼロの間をウロウロするだけかもしれません。
逆に、「褒められること」だけしか知らなければ、プラマイゼロからプラス100度の範囲でしか、自分の感情をコントロールできないかもしれません。
どちらか一方に偏った経験は、心の「可動域」を狭めてしまいます。それは、まるで片方の筋肉ばかりを鍛えて、バランスを失ったアスリートのようなものです。
教育や育成の過程においては、褒めることも叱ることも、両方必要であり、むしろ両極端を経験させるくらいの覚悟が必要だと。
もちろん、人格否定やパワハラは論外ですが、適切なフィードバックとしての「叱咤」は、成長にとって不可欠なスパイスなのです。この振れ幅への「慣れ」こそが、精神的なタフさを育む第一歩となります。
2.「自分軸」で評価する力を育む ~ 内なる声に耳を澄ます
そして、今回のコラムで最もお伝えしたい、二つ目の重要な要素。それが、「自分軸」を確立することの重要性です。
「褒める」という行為一つをとっても、実は2つの側面があります。 一つは、「他人から褒められる」こと。これは「他人軸」の評価です。上司に「よくやった!」と言われれば嬉しい。お客様に「ありがとう、助かったよ!」と感謝されれば、飛び上がるほど嬉しい。これは、強力なモチベーションになります。
しかし、もう一つ、非常に重要な「褒める」があります。それは、「自分で自分自身を褒める」ことです。
「よし、今回のプレゼン、準備も万端だったし、堂々と話せたぞ!俺、なかなかやるじゃないか!」「目標達成はできなかったけど、あの難しい局面で諦めずに粘り強く交渉し続けた自分は、間違いなく成長している!」これは、「自分軸」の評価です。
同様に、「怒る(叱る)」という行為にも、2つの側面があります。 一つは、「他人から怒られる(叱られる)」こと。「他人軸」の評価です。先生に注意された、上司に厳しく指摘された、お客様からお叱りを受けた…。これは辛く、凹みます。
しかし、もう一つは、「自分で自分自身を怒る(戒める)」ことです。
「あんなミスをしてしまうなんて、準備不足も甚だしい。プロとして恥ずかしい。次は絶対に同じ過ちを繰り返さないぞ!」「あの時、もっと勇気を出して一歩踏み込んでいれば、結果は変わったかもしれない。まだまだ自分は甘いな…!」これは、「自分軸」による内省と改善への決意です。
私が多くの営業や、悩みを抱える人々と接していて強く感じるのは、この「自分軸で自分を評価し、律する力」がいかに大切か、ということです。
他人からの評価(他人軸)は、外的要因によって大きく変動します。気まぐれな上司、移り気なお客様、市況の変化…。そんな不確実なものに自分の価値判断を委ねていては、いつまで経っても心は安定しません。
本当に大切なのは、「他人にどう見られるか」ではなく、「自分自身が、自分の行動や結果に対して、どう向き合い、どう評価し、次にどう繋げていくか」という、内なる基準(自分軸)をしっかりと持つことなのです。
なぜ「自分軸」が育たないのか? 2つの落とし穴
では、なぜ多くの人が、この「自分軸」をうまく形成できず、「他人軸」に振り回されてしまうのでしょうか? 私は、そこに大きく2つの要因があると考えています。
要因1:すべての評価を「二者間の関わり」だけで捉えてしまう
一つは、何か出来事があった時に、その評価や原因を、常に「自分と、特定の誰か(例えば、上司の田中さん)」という二者間の関係性の中だけで完結させてしまう思考のクセです。
「田中さんに褒められたから、これは良いことだ」「田中さんに怒られたから、自分はダメなんだ」。すべてのベクトルが、常に「田中さん」という外部の存在に向いてしまっている。
そこには、「今回の件で、田中さんはそう言ったけれど、自分自身はどう感じたのか?」「田中さんの評価は一旦置いておいて、自分としては、今回の行動のどこに改善点があり、どこに成長があったと考えるか?」といった、自分の内面に向き合う視点がすっぽりと抜け落ちてしまっているのです。
これでは、いつまで経っても「田中さん(=他人)の顔色をうかがう」という思考パターンから抜け出せません。
要因2:「自分の将来(成長)」という時間軸が欠落している
もう一つの要因は、物事をあまりにも「刹那的」に捉えすぎていて、「自分の将来的な成長」という長い時間軸の視点が欠けていることです。
田中さんに褒められたら、「やったー!最高!」と舞い上がり、怒られたら「うわー、最悪だ…もう終わりだ…」と世界の終わりのように落ち込む。もちろん、目の前の出来事に一喜一憂する感情は自然なものです。しかし、それ「だけ」で終わってしまっては、非常にもったいない。
本来であれば、「確かに、今、田中さんには怒られたけれど、この失敗から学べることは何だろうか?」「この経験を、自分の将来の営業スキル向上や、人間的な成長にどう活かせるだろうか?」といった、未来の自分への「投資」という視点があって然るべきです。
今の瞬間的な感情に流されるだけでなく、「この経験は、数年後の自分の戦闘力を上げるために、どんな意味があるのか?」という長期的な視点を持つこと。これが、「自分軸」を育む上で不可欠な要素なのです。
「自分軸」と「他人軸」の理想的な“マリアージュ”
ここまで「自分軸」の重要性を強調してきましたが、誤解しないでいただきたいのは、「他人軸が全く不要だ」と言っているわけではない、ということです。むしろ逆です。
健全な成長と社会的な成功のためには、「自分軸」と「他人軸」の両方をバランス良く持ち合わせ、状況に応じて適切に使い分ける、あるいは自然と調和させていくことが不可欠なのです。
「自分軸」を持つことの最大のメリットは、何と言っても「精神的なタフさ」です。自分の内面に確固たる価値基準があれば、他人から多少何を言われようと、褒められようと貶されようと、そこで心が大きく揺らぐことはありません。
「まあ、人はそう言うかもしれないけど、自分はこう思うから、これでいいんだ」と、ドンと構えていられます。これは、ストレスの多い現代社会を生き抜く上で、非常に重要な力です。
しかし、一方で「他人軸」を持つことも、社会で生きていく上では極めて重要です。特に、私たち営業という仕事は、お客様に喜んでいただき、満足していただいて、初めて契約という成果に繋がります。
お客様が何を求めているのか、どうすれば喜んでくれるのか、といった「相手の視点(他人軸)」を持たずに、独りよがりな「自分軸100%」の営業をしていては、いくらタフであっても、お客様からは嫌われ、社内でも評価されず、結局は成果に結びつかないでしょう。
問題なのは、この「自分軸」と「他人軸」のどちらか一方に偏ってしまうこと。あるいは、どの場面でどちらを優先すべきか、という「選択」を間違えてしまうセンスのなさです。
そして、この「選択を間違える」原因をさらに掘り下げていくと、その根底には、やはり「自分軸の弱さ」があることが多い、と私は見ています。自分の中にしっかりとした軸がないから、他人の評価や外部の状況に簡単に流され、その場その場で場当たり的な対応しかできなくなってしまうのです。
では、理想的な状態とは、どのようなものでしょうか?
それは、「自分軸」と「他人軸」が、意識的に「よし、ここは自分軸でいこう!」「よし、ここは他人軸を優先しよう!」とガチガチに切り替えるのではなく、もっと自然に、無意識のうちに混ざり合い、調和している状態です。
「お客様(他人軸)のために、一生懸命提案を考えている。でも、それは結局、自分の営業としての成長(自分軸)にも繋がっているんだよな」「上司(他人軸)から厳しいフィードバックを受けた。悔しいけど、これは自分(自分軸)がもっと高みを目指すために必要な試練なんだ」
このように、他人を意識しつつも、それが最終的には自分の成長や納得感に繋がっている。自分軸と他人軸が、対立するものではなく、互いを補い合い、高め合う関係になっている。
この「どっちもあって、どっちも大事」という感覚、この絶妙な「マリアージュ感」こそが、私たちが目指すべき、真に成熟した精神状態ではないでしょうか。
真の「褒める教育」「叱る教育」とは? ~ 部下の「自分軸」を呼び覚ます
さて、冒頭の「褒める教育、怒る教育」というテーマに立ち返りましょう。
ここまでの話を総括すると、部下を育成する上で私たちが目指すべきゴールは、以下の2点に集約されます。
- まず、褒められる喜び(プラスの温度)と、叱られる悔しさ(マイナスの温度)の両方を経験させ、「感情の振れ幅」に慣れさせること。 どちらか一方に偏ることなく、両極端の経験を積ませることで、精神的なタフさとバランス感覚を養います。
- そして、その経験を通じて、いかに「自分軸」の感覚を持たせるか。 つまり、褒められる・叱られるという出来事に対して、他人からの評価だけでなく、「自分で自分をどう評価するか」「自分で自分をどう律するか」という内なる視点を、いかに気づかせ、形成させるか。
これこそが、教育・育成の核となるべきポイントだと、私は強く信じています。単に褒め言葉を並べ立てたり、感情的に怒鳴りつけたりするのではなく、一つひとつの出来事を、部下自身の「自分軸」を育むための貴重な機会として捉え、問いかけ、対話し、内省を促していく。
それこそが、真の意味での「褒める教育」であり、「叱る教育」なのではないでしょうか。
あなたの「次の一歩」:部下の「内なる声」に火をつける
この長いコラムを最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。きっと、あなたの頭の中では、部下の顔や、過去の指導シーンが色々と駆け巡っていることでしょう。
最後に、明日からすぐに実践できる、具体的な「次の一歩」を提案させてください。
次に、あなたの部下が何か小さな成果を上げて、あなたが褒めてあげたい、と感じた時。あるいは、何かミスをして、フィードバックをしなければならない、と感じた時。
いつものように、あなたの評価や指示を伝える前に、まず一呼吸置いて、こう問いかけてみてください。
(成果を上げた時) 「〇〇さん、素晴らしい結果だね!本当によくやったと思うよ。ところで、今回の成功について、〇〇さん自身は、どのあたりが一番うまくいったと感じてる? そして、その経験から学んで、次に活かせそうなことって何だろう?」
(ミスをした時) 「〇〇さん、今回は残念な結果になってしまったね。気持ちは分かるよ。ただ、この経験を次に活かすために、〇〇さん自身は、今回の原因はどこにあったと考えてる? そして、もしもう一度同じ状況になったら、今度はどう改善しようと思う?」
ただ褒める、ただ叱る、のではなく、彼ら自身に「内省」を促し、「自己評価」の機会を与え、そして「次への学び」を引き出すような問いかけをする。
この小さな問いかけの積み重ねが、部下の心の中に眠る「自分軸」という名の小さな炎に、そっと酸素を送り込み、やがては自ら燃え盛る大きな力へと育てていく、最初の一歩になるはずです。
「他人軸」に揺らがない、最強の営業チームを創るために
あなたの会社の営業チームは、上司の顔色やお客様の機嫌、あるいは刹那的な成功や失敗といった「他人軸」に振り回されることなく、一人ひとりが確固たる「自分軸」を持って、日々の営業活動に取り組めているでしょうか?
もし、
- 部下がなかなか自律的に動いてくれず、指示待ち状態になっている…
- 褒めないと頑張れない、叱るとすぐに凹んでしまう、そんな打たれ弱い社員が多い…
- チーム全体の売上が、個々のモチベーションや外部環境に大きく左右されて不安定…
- 「自分軸」を持ち、自ら考え、行動し、粘り強く契約を獲得できる、真に強い営業組織を本気で作りたい…
と、心の底から願う経営者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
トレテクは、単に「褒め方」「叱り方」といった表面的なテクニックを教えるのではありません。あなたの会社の文化や、メンバー一人ひとりの特性を深く理解した上で、彼らの内なる「自分軸」を呼び覚まし、自律的な成長を促すための、具体的な育成戦略と、その実践をサポートします。
「他人軸」に揺らがない強さと、「自分軸」で未来を切り拓く主体性。その両方を兼ね備えた、最強の営業チームを、一緒に創り上げていきませんか?
まずは、60分間の無料オンライン相談で、貴社の現状の課題や、目指したい未来について、気軽にお話しいただければと思います。無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。下記のリンクから、今すぐ無料相談にお申し込みいただけます。
また、日々の営業活動のヒントや、コンサルティングの現場からの気づきなどを、Instagramでも発信しています。よろしければ、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。
あなたの、そして貴社の営業が、お客様から心から信頼され、選ばれ続ける存在になるためのお手伝いができることを、楽しみにしています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。