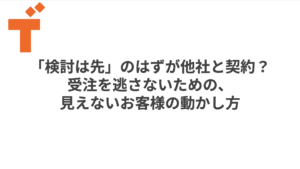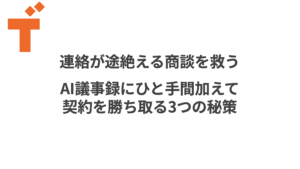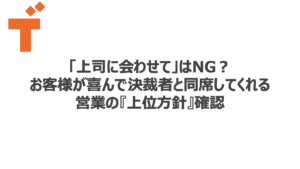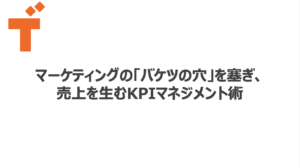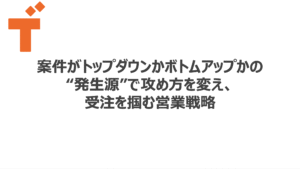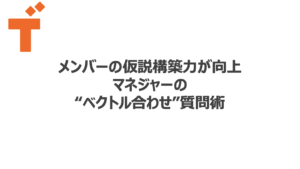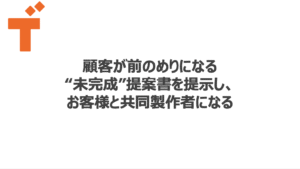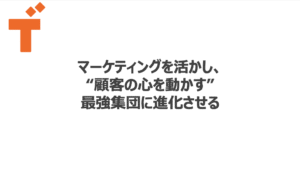お客様の「真の課題」は迷路の入り口!?お客様が能動的になる“本当の課題”の見つけ方
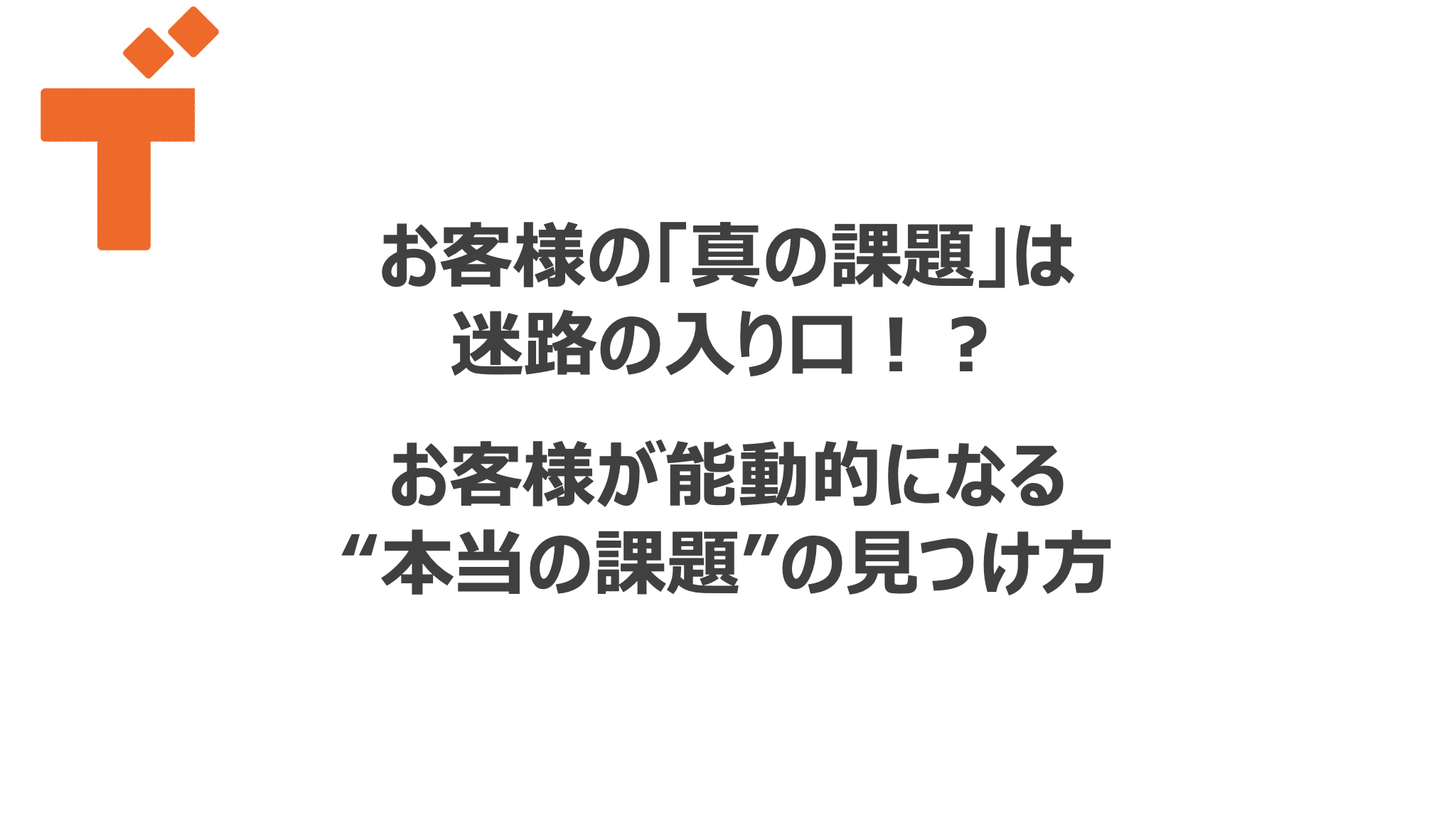
「御社の課題は何ですか?」
営業の現場で、これまで幾度となく繰り返されてきたであろう、この質問。しかし、この問いに対して、あなたの期待する答えが返ってくることは、どれほどあるでしょうか。
「うーん、まあコスト削減かな…」
「もっと人を増やしたいんだけど、採用がうまくいかなくて…」
返ってくるのは、どこか当たり障りのない、表面的な答えばかり。その言葉を信じて提案を練り上げても、お客様の心には響かず、商談は空振り。受注には程遠い結果に終わる…。
そんな経験に、多くの経営者や営業マネジャーは頭を悩ませているはずです。お客様は、なぜ「本当の課題」を教えてくれないのでしょうか。いや、そもそもお客様自身、それに気づいていないのかもしれません。
この記事は、そんなお客様の「心の奥底にある課題」を捉えきれず、もどかしい思いをしている方々のために書きました。
この記事を読めば、お客様自身も言語化できていない「真の課題」を特定し、お客様が自ら「この問題を、あなたと一緒に解決したい!」と能動的に動き出すための、全く新しいヒアリングの視点が手に入ります。
「真の課題」を追い求めて迷子になる営業たち
多くの真面目な営業担当者ほど、「お客様の真の課題を見つけなければ」という強迫観念にも似た使命感を持っています。その姿勢は、もちろん素晴らしい。しかし、ここで一つのワナにはまりがちです。
そのワナとは、「真の課題=問題の根本原因」という捉え方です。
有名なトヨタの「なぜなぜ5回」のように、「なぜ?」を繰り返して深掘りすれば、いつか根本原因にたどり着ける、と。
しかし、現実はそう単純ではありません。5回掘れば必ず真実にたどり着く保証はどこにもないし、3回では不十分だという根拠もない。そもそも、何が「真実」かを客観的にジャッジできる人間など、どこにもいないのです。
この「深さ」を基準にしてしまうと、営業は非常に苦しい戦いを強いられます。「自分が見つけたこの課題は、まだ浅いのではないか…」「もっと深掘りしないと…」と、終わりのない禅問答に陥ってしまう。これでは、いつまで経ってもお客様に価値を届けることはできません。
では、私たちは「真の課題」を、どのように捉えれば良いのでしょうか。
定義を変えれば、世界が変わる。「真の課題」の新しい基準
ここで私は、課題の「深さ」で判断するのをやめて、全く違う角度から光を当てることを提案したいと思います。
それは、「その課題が特定されたとき、お客様が納得して、解決のために気持ちよく“動き出せる”かどうか」を基準にする、という考え方です。
たとえそれが、第三者から見れば「まだ表面的だ」と指摘されるような課題だったとしても、お客様自身が「それだ!それが私たちの問題だったんだ!」と心の底から腹落ちし、組織全体が「よし、この課題を解決しよう!」と一つの方向を向いて動き出すのであれば、それは紛れもなく、そのお客様にとっての「真の課題」なのです。
逆に、どれだけ論理的に正しく、根本的だと思われる原因を指摘したところで、お客様が「うーん、まあ、そうかもしれないけど…」と腑に落ちず、行動に移せないのであれば、それは契約にも売上にも繋がらない、ただの「正論」でしかありません。
課題が特定されることで、なぜ組織は「動き出せる」ようになるのでしょうか。そこには、3つのメカニズムが働いています。
積もり積もった「ストレス」が解消されるから
その課題が放置されることで、社内の多くの人々が、目には見えないストレスを日々感じ続けていた、というケースです。
「あの件、どうなってるんだ…」「またこの問題か…」といったモヤモヤが、その課題を解決することでスッキリ解消されると分かったとき、「それならやろう!」という強い動機が生まれます。
組織内で「合意形成」ができるから
例えば、営業部門は「商品が悪いから売れない(開発が課題だ)」と思い、開発部門は「営業力が足りないからだ(営業が課題だ)」と思っている。これでは、お互いを非難し合うだけで、一歩も前に進めません。
ここで重要になるのが、客観的な情報(ファクト)です。例えば、「お客様相談窓口に寄せられたクレームの7割が、製品の〇〇という機能に関するものだった」という事実や、「Webサイトの特定のページで、90%のユーザーが離脱している」という数字。
こうした誰もが認めざるを得ない「事実」を土台にすることで、感情的な対立を乗り越え、「なるほど、これが我々共通の課題だな」という合意が生まれ、組織は動き出せるのです。
複雑な「しがらみ」が解きほぐされるから
社内の人間関係や部署間の力学、錯綜する情報によって、問題の構造そのものが、中にいる当事者には見えなくなってしまっていることがあります。
外部のコンサルタントのような客観的な視点を持つ人間が、その絡み合った糸を解きほぐし、「問題の本質は、実はここにあったんですね」と示すことで、霧が晴れたように視界が開け、当事者たちは「それなら、こう動けばいいのか!」と納得して行動できるようになります。
このように、お客様が「動ける」状態になることこそが、「真の課題」が捉えられた証拠なのです。この定義に立てば、課題探しのゴールは非常に明確になります。
「課題」を聞くのをやめると、「真の課題」が見えてくる
では、どうすればお客様が「動き出せる」真の課題にたどり着けるのでしょうか。
多くの営業担当者は、「御社の課題は何ですか?」と、課題そのものについて質問します。しかし、このアプローチでは表面的な答えしか返ってきにくいことは、すでにお話しした通りです。
ここで、視点を180度変えてみましょう。
課題そのものを聞くのではなく、「なぜ、その課題の解決に向けて“動き出せない”のですか?」という、行動を阻害している要因を探るのです。
この質問をすると、お客様からは決まって二つの答えが返ってきます。
「いやぁ、忙しくて時間がないんですよ」
「それをやるための予算がないんです」
しかし、ここで「そうですか、では仕方ないですね」と引き下がってはいけません。これは、真の課題を隠すための、最も便利な言い訳に過ぎません。
時間は、誰にでも平等に24時間あります。「時間がない」というのは、「他の何かに時間を使っている」ということに他なりません。予算も同様です。会社が存続している以上、全くお金がないということは稀で、「他の何かに予算を割り当てている」のです。
つまり、「時間がない」「お金がない」という言葉の裏には、「その課題は、他の何かよりも“優先順位が低い”」という、動かぬ事実が隠れています。
究極の質問:「その課題の代わりに、何を優先しているのですか?」
ここまで来れば、あなたが本当に探るべき核心が見えてきます。それは、お客様の「優先順位」です。
お客様の心の奥底に対し、こう問いかけてみてください。
「その課題の解決を後回しにしてまで、高い優先順位に置かれているものは、一体何なのだろうか?」
この「代わりに優先されているもの」にこそ、その会社のカルチャー、経営者の価値観、そして社内の見えない「しがらみ」といった、真の課題を解き明かすための、最大のヒントが眠っています。
例えば、「今は全社を挙げて、新しい基幹システムの導入プロジェクトに取り組んでいるんです」という答えが返ってきたとします。そこで「そうですか」と終わるのではなく、「なぜ今、そのプロジェクトが最も優先されているのですか?」と一歩踏み込む。
そうすることで、お客様の組織が本当に価値を置いていること、本当に解決したいと願っていることの輪郭が、浮かび上がってくるのです。
まずは「今、一番エネルギーを注いでいること」を聞いてみよう
「真の課題」を見つけるヒアリングは、宝探しに似ています。しかし、やみくもに地面を掘る必要はありません。
宝が埋まっている場所を示す「地図」は、お客様の「行動」と「優先順位」の中に、必ず隠されています。
とはいえ、いきなり「何を優先しているんですか?」と聞くのは、少しハードルが高いかもしれません。
でしたら、次の商談で、こう試してみてはいかがでしょうか。
お客様が口にした「課題」を一通り聞いた後、もし会話が止まりそうになったら、こう質問するのです。
「ちなみに、今、御社が組織として最も時間とエネルギーを注いでいるプロジェクトや取り組みは何ですか?」
この質問一つで、これまで見えていなかったお客様の「本音」や「本気」が顔を覗かせるはずです。それは、あなたの営業を、単なる“御用聞き”から、お客様の事業の根幹を共に考える“戦略的パートナー”へと変える、魔法の問いになるかもしれません。
お客様が能動的になる「課題」を見つけ出し、会社の未来を作る
表面的な課題解決で終わるのではなく、お客様の事業の根幹に関わり、心から信頼されるパートナーでありたい。そして、自社の営業担当者を、そんな存在へと成長させたい。
もし、そう本気でお考えの経営者、マネジャーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
トレテクは、小手先のテクニックではない、本質的なコミュニケーションを通じて、あなたの会社の売上と成長に貢献することをお約束します。
まずは60分間の無料オンライン相談で、貴社の現状と未来について、お聞かせください。
▶︎▶︎ 60分無料オンライン相談はこちらから ◀︎◀︎
日々の活動のヒントは、Instagramでも発信中です。
▶︎▶︎ Instagramで活動をチェックする ◀︎◀︎
最後までお読みいただき、ありがとうございました。